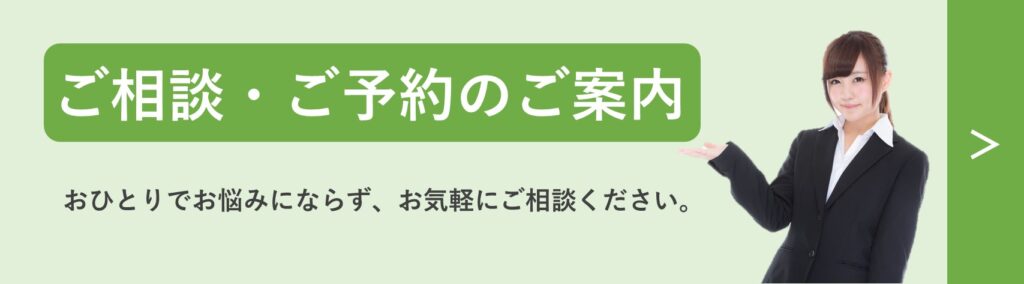目次
建設現場における労災事故について
建設現場で働く皆さんにとって、労働災害は決して他人事ではありません。高所での作業、重機の操作、危険な資材の取り扱いなど、建設現場には常にリスクが潜んでいます。そして実際に事故が発生した場合、多くの方が「労災保険に入っているから大丈夫」と考えがちです。しかし、本当にそれだけで十分なのでしょうか。
私は福井県で15年以上、弁護士として活動し、数多くの労働災害案件を手がけてきました。その経験の中で痛感するのは、労災保険だけでは被害者の方が受けるべき適切な補償を得られないケースが非常に多いということです。特に建設現場での事故では、会社の安全対策が不十分だったために起きた事故も少なくありません。
そこで、本記事では建設現場でよくある事故から、労災申請の流れについて解説します。労災申請で納得いくものにならなかった場合の損害賠償請求についても触れていますので、参考にしてください。
1 建設現場での仕事中の事故による怪我は労災である
仕事中の事故による怪我は基本的に労災です。ですから、迅速に労災保険の申請を行ってください。

もし、会社に安全配慮義務違反等があれば、損害賠償請求も可能です。安全配慮義務とは、使用者が労働者の心身の健康と安全を守るための法的義務です。労働契約法第5条と労働安全衛生法第3条に基づき、使用者は労働者が安全に働ける環境を整備し、事故防止や健康管理に努めなければなりません。
具体的には、物理的な職場環境の整備、事故防止策の実施、心身の不調への対策などが含まれます。これらは「健康配慮義務」と「職場環境配慮義務」に分類されます。
安全配慮義務違反には直接的な罰則はありませんが、労働安全衛生法違反には罰金刑があります。また、義務違反により労災事故が発生した場合、損害賠償請求が可能となります。
違反となるケースは、使用者が予見可能で防止できたにもかかわらず、必要な対策を怠ったことで労働者の安全が脅かされた場合です。使用者は労働者の安全と健康を確保するため、適切な措置を講じる必要があるのです。
2 建設現場では「墜落・転落」に注意
建設現場における労災事故は、「墜落・転落」が最も多いとされています。全国仮設安全事業協同組合による調査では、死亡原因の4割が墜落・転落とされています。
【墜落・転落が建設業労働死亡災害死亡原因・事故の型別に占める割合】
・墜落・転落…86人
・その他…137人
引用元:後を絶たない足場からの墜落・転落災害 | 全国仮設安全事業協同組合
墜落・転落の発生箇所においては、足場、屋上、屋根など、高所からの事故が約2割前後です。使用者は、これらのことを踏まえて、高所での作業に気を配り、安全策を講じなければなりません。
3 建設現場で事故が起きた場合の労災申請の流れ
労災申請の基本的な流れは、以下のとおりです。

【 会社への報告 】
労働災害が発生したら、まず会社に詳細を報告します。これにより、会社は労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出できます。

【 医療機関の受診 】
労災保険指定医療機関または最寄りの取り扱い病院で診察を受けます。指定医療機関では医療費が無料になり、手続きもスムーズです。

【 必要書類の準備と提出 】
基本的に会社が手続きを行いますが、自身で行う場合もあります。厚生労働省のウェブサイトから必要な書類をダウンロードし、作成します。給付の種類によって必要な書類が異なるので注意が必要です。

【 労働基準監督署への請求書提出 】
作成した書類を労働基準監督署に提出します。一部の給付は病院に直接提出する場合があります。

【 労働基準監督署による調査 】
提出された書類をもとに、労災に該当するかどうかの調査が行われます。事故型の労災は比較的短期間で、病気型の労災は6ヶ月程度かかることがあります。

【 給付決定と開始 】
労災と認められれば給付が開始されます。不支給の決定の場合は、審査請求や再審査請求、行政訴訟などの方法で不服を申し立てることができます。
なお、労災の申請手続きは、基本的に被災労働者本人または遺族が行います。ただし、会社の人事担当者が代行することもあります。アルバイトや日雇い労働者も、雇用契約があれば補償対象となります。派遣労働者の場合は、本人または派遣元の会社が手続きを行います。
4 建設現場での事故やケガで後遺障害が残った場合に当事務所ができること

建設現場での事故で後遺障害が残った場合、当事務所は以下のような重要なサポートを提供できます
賠償金請求のサポート
・保険会社との交渉代行
・適正な賠償金額の算定と請求
後遺障害等級の認定サポート
・正当な評価を受けるための書類準備
・医療機関との連携
・労働基準監督署での面談準備と同行
複数の賠償ルートの活用
・労災保険や第三者賠償請求など、最も有利な手続きの選択と適用
法的対応
・損害賠償請求が難航した場合の訴訟対応
専門的なアドバイス
・医師の障害診断書の適切性チェック
・症状の適切な説明方法の指導
当事務所は、被害者の権利を最大限に保護し、適切な補償を受けられるよう、専門的な知識と経験を活かしてサポートします。
5 会社に損害賠償請求をする選択肢も検討
建設現場での事故における労災補償には限界があります。労災保険は慰謝料を含まず、休業補償も事故前の収入全額には及びません。さらに、将来の収入減少に対する補償も十分とは言えません。
このような不足を補うため、会社の安全配慮義務違反が認められる場合、労働者は会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。これにより、労災保険では補償されない慰謝料や、休業補償の不足分、後遺障害による逸失利益などの賠償を求めることができます。
安全配慮義務とは、労働者の生命と健康を危険から保護するよう会社が配慮する義務を指します。この義務違反は主に労働安全衛生法令違反の形で現れます。例えば、労働安全衛生規則519条は、2メートル以上の高所作業における墜落防止措置を義務付けています。
建設現場での墜落・転落事故においては、たとえば、以下のような例が安全配慮義務違反になる可能性があります。
・2m以上の高所作業での転落防止措置の不備
・危険な作業指示(荷物を持っての昇降など)
・不適切な器具の使用(天板に乗る、脚立に跨る等)
・不整形地での適切でない脚立の使用
・はしごの固定不備
・器具自体の不具合
会社が法令に基づく安全対策を怠っていた場合、労働者は労災保険の補償を超える損害について会社に賠償を求める権利があります。
6 建設現場での事故でご家族が亡くなってしまった際に当事務所ができること

建設現場での事故でご家族を亡くされた場合、まず、損害賠償請求のサポートとして、労災保険や第三者賠償請求の手続きを支援し、適切な賠償額を算出します。
また、会社や保険会社側との交渉を代行し、ご遺族の権利を守ります。
労災保険に関しては、葬祭料や遺族補償給付の申請手続きをサポートし、就学中のお子様がいる場合は労災就学援護費の制度についてもアドバイスします。事故原因が会社の安全配慮義務違反や他の従業員の過失による場合、会社に対する損害賠償請求も支援します。これにより、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益などの請求が可能となります。
過失割合が問題となる場合は、必要な証拠を集め、被害者側の権利を守るための法的主張を行います。さらに、悲しみの中にあるご遺族の方々に寄り添い、複雑な法律手続きをスムーズに進めるための精神的サポートも提供します。
まとめ
建設現場における労災事故は、決して他人事ではありません。
労災申請は会社への報告から始まり、医療機関での受診、必要書類の準備・提出、労働基準監督署での調査を経て認定・不認定が決定されます。
そして重要なのは、労災保険だけでは十分な補償を受けられない場合が多いということです。慰謝料は支給されませんし、休業補償も事故前の収入全額には及びません。会社の安全配慮義務違反が認められれば、労災保険に加えて損害賠償請求も可能になり、より充実した補償を受けることができます。
当事務所は福井県内で15年以上にわたり、数多くの労災案件を手がけてきました。建設現場の労災事故でお困りの方、ご家族を亡くされた方、後遺障害でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。