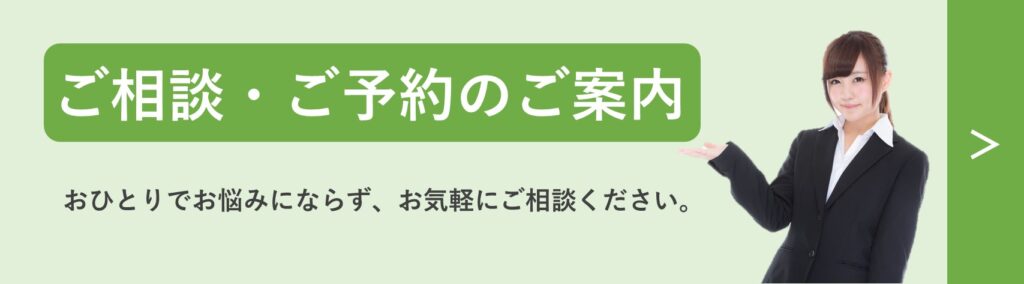目次
運送業における労災事故について
運送業で働いていると、「仕事中に怪我をしても労災はおりるのだろうか」「事故に遭った場合、どのような補償が受けられるのだろうか」といった不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実際、運送業は他の業種と比べて労災事故の発生率が高く、特に荷物の搬入出作業中の事故が頻繁に起こっています。しかし、多くの労働者の方が労災制度について十分な知識を持っておらず、適切な補償を受けられずに泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
運送業における労災事故は、正しい知識と適切な手続きを行うことで、労災保険給付はもちろん、場合によっては会社に対する損害賠償請求も可能になります。
この記事では、運送業で起こりやすい労災事故の種類から申請手続き、さらには十分な補償を受けるための方法まで、実務経験に基づいて詳しく解説していきます。
1 仕事中の事故による怪我は労災であること

運送業における仕事中の事故は、原則として労働者災害補償保険法(労災法)に基づく労災に該当します。労災法において、労働者が業務災害または通勤災害によって負傷した場合、労災保険の給付対象となると規定されています。
業務災害とは、労働者が事業主の指示または監督下で業務を行っている最中に発生した災害を指し、通勤災害は、自宅から職場、または職場間を合理的な経路で移動中に発生した事故が対象となります。
事業主の明示的な指示だけでなく、業務に密接に関連する範囲で発生した災害も含まれます。また、通勤災害は「合理的な経路および方法」に限られるため、これらを逸脱すると対象外となります。
また、事業主には、労働契約法(第5条)に基づき、労働者の安全を確保する「安全配慮義務」が課されています。この義務に違反した場合、労災保険給付に加えて、会社に対して損害賠償請求が可能です。
例えば、トラック運転中の過労や荷物の搬入作業中の安全対策不備が原因で事故が発生した場合、事業主の責任が問われることがあります。事業主は、労働者が安全に作業できる環境を整える義務があるため、この義務を怠った場合には、労働者は法的な救済を求めることが可能です。
ただし、労災保険給付と損害賠償は一部補完関係にあり、二重取り(重複して同一の損害について受け取ること)はできないので、注意が必要です。
2 運送業は交通事故よりも荷物搬入出時の事故が非常に多いこと

運送業において、最も想像しやすい事故はトラック運転中の交通事故です。しかし実際には、労災事故の多くは荷物の積み下ろしや搬入出時に発生しています。
こうした作業は、トラックの荷台や倉庫内で行われることが多く、フォークリフトや手作業で重い荷物を扱う際に怪我をするリスクが高まります。特に、重い荷物を無理な体勢で持ち上げることによる腰痛や、荷物が落下した際に起こる怪我が一般的です。
これらの事故は、労働者災害補償保険法に基づき、労災認定される可能性が高いです。
このような荷物の積み下ろし作業中の事故は、「労働安全衛生法」に基づく安全対策が求められます(労働安全衛生法第59条)。具体的には、作業手順の教育や、適切な安全装置の使用が義務づけられています。
また、フォークリフトの操作に関する資格取得や、作業現場での安全確認など、労働者が安全に作業を行うための環境整備が必要です。
墜落・転落事故
運送業の現場では、墜落や転落による事故が頻繁に発生します。
特に、倉庫や配送センターなどで高所作業を行う際や、フォークリフトを使用する場面でリスクが高まります。フォークリフトは、荷物を高い場所に運ぶために使われることが多いですが、運搬中に本来人が乗るべきでない箇所に人が乗ったまま作業を続けると、転落事故の原因となります。
また、高所での荷積み作業中にバランスを崩して落下するケースも多く見られます。
このような墜落や転落事故に対しては、労働安全衛生法が規定する高所作業の安全基準に基づく対策が必要です。
例えば、安全帯や足場の設置、フォークリフト使用時の安全講習などが義務づけられています。これに違反した場合、事業主には労働者に対する損害賠償責任が生じる可能性があります。現場では、定期的な安全チェックや作業者への教育が必須です。
激突される事故
フォークリフトの操作ミスや視界不良による事故も、運送業では非常に多く発生しています。フォークリフトは、倉庫内で頻繁に使用される機械ですが、運転者の不注意や、周囲の労働者の無警戒な動きが原因で、人との衝突事故が起こりやすいです。
例えば、フォークリフトで荷物を運搬中、視界が遮られている状態で誤って人に衝突するケースがしばしば見られます。こうした事故を防ぐためには、労働安全衛生法に基づくフォークリフト運転者への教育と、倉庫内の安全対策が必要です。
運転者には、フォークリフト運転技能講習の受講が義務づけられており、運転中は視界確保や周囲の確認が不可欠です。また、倉庫内には警告表示や一方通行などのルールを設け、作業員が事故に巻き込まれないような動線の整備も重要です。
3 労災申請(認定)の流れ
労災事故が発生した場合、労災保険給付を受けるためには労災認定の手続きを行う必要があります。労災認定の手続きは、以下の手順で進められます。

【 会社への報告 】
労働災害が発生したら、まず会社に詳細を報告します。これにより、会社は労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出できます。

【 医療機関の受診・治療 】
労災保険指定医療機関または最寄りの取り扱い病院で診察を受けます。指定医療機関では医療費が無料になり、手続きもスムーズです。

【 必要書類の準備と提出 】
基本的に会社が手続きを行いますが、自身で行う場合もあります。厚生労働省のウェブサイトから必要な書類をダウンロードし、作成します。給付の種類によって必要な書類が異なるので注意が必要です。

【 労働基準監督署への請求書提出 】
作成した書類を労働基準監督署に提出します。一部の給付は病院に直接提出する場合があります。
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・事業主証明
・医師の診断書

【 労働基準監督署による調査・審査 】
提出された書類をもとに、労災に該当するかどうかの調査が行われます。事故型の労災は比較的短期間で、病気型の労災は6ヶ月程度かかることがあります。
労働基準監督署は、労災が業務中または通勤途中に発生したかどうか、事故の原因が業務に関連しているかを調査します。この調査には、事業主や事故現場の証言、診断書などの証拠資料が用いられます。調査の結果、労働基準監督署が支給または不支給の判断を行い、労働者に決定通知が送られます。

【 労災認定・不認定の決定 】
労災と認められれば給付が開始されます。不支給の決定の場合は、審査請求や再審査請求、行政訴訟などの方法で不服を申し立てることができます。
労災保険給付が認められた場合、厚生労働省より指定された口座に給付金が振り込まれます。
なお、労災申請には「事業主証明」の取得が必要ですが、事業主が協力しない場合でも、労働者は直接申請が可能です。
4 運送業現場での事故やケガで後遺障害が残った場合に当事務所ができること

運送業現場での事故で後遺障害が残った場合、当事務所は以下のような重要なサポートを提供できます
賠償金請求のサポート
・保険会社との交渉代行
・適正な賠償金額の算定と請求
後遺障害等級の認定サポート
・正当な評価を受けるための書類準備
・医療機関との連携
・労働基準監督署での面談準備と同行
複数の賠償ルートの活用
・労災保険や第三者賠償請求など、最も有利な手続きの選択と適用
法的対応
・損害賠償請求が難航した場合の訴訟対応
専門的なアドバイス
・医師の障害診断書の適切性チェック
・症状の適切な説明方法の指導
当事務所は、被害者の権利を最大限に保護し、適切な補償を受けられるよう、専門的な知識と経験を活かしてサポートします。
5 会社に損害賠償請求をする選択肢も検討
運送業現場での事故における労災補償には限界があります。労災保険は慰謝料を含まず、休業補償も事故前の収入全額には及びません。さらに、将来の収入減少に対する補償も十分とは言えません。
このような不足を補うため、会社の安全配慮義務違反が認められる場合、労働者は会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。これにより、労災保険では補償されない慰謝料や、休業補償の不足分、後遺障害による逸失利益などの賠償を求めることができます。
安全配慮義務とは、労働者の生命と健康を危険から保護するよう会社が配慮する義務を指します。この義務違反は主に労働安全衛生法令違反の形で現れます。
会社が法令に基づく安全対策を怠っていた場合、労働者は労災保険の補償を超える損害について会社に賠償を求める権利があります。
6 運送業現場での事故でご家族が亡くなってしまった際に当事務所ができること

運送業現場での事故でご家族を亡くされた場合、まず、損害賠償請求のサポートとして、労災保険や第三者賠償請求の手続きを支援し、適切な賠償額を算出します。
また、会社や保険会社側との交渉を代行し、ご遺族の権利を守ります。
労災保険に関しては、葬祭料や遺族補償給付の申請手続きをサポートし、就学中のお子様がいる場合は労災就学援護費の制度についてもアドバイスします。事故原因が会社の安全配慮義務違反や他の従業員の過失による場合、会社に対する損害賠償請求も支援します。これにより、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益などの請求が可能となります。
過失割合が問題となる場合は、必要な証拠を集め、被害者側の権利を守るための法的主張を行います。さらに、悲しみの中にあるご遺族の方々に寄り添い、複雑な法律手続きをスムーズに進めるための精神的サポートも提供します。
まとめ
運送業における労災事故は、決して他人事ではありません。
労災申請は会社への報告から始まり、医療機関での受診、必要書類の準備・提出、労働基準監督署での調査を経て認定・不認定が決定されます。
そして重要なのは、労災保険だけでは十分な補償を受けられない場合が多いということです。慰謝料は支給されませんし、休業補償も事故前の収入全額には及びません。会社の安全配慮義務違反が認められれば、労災保険に加えて損害賠償請求も可能になり、より充実した補償を受けることができます。
当事務所は福井県内で15年以上にわたり、数多くの労災案件を手がけてきました。運送業の労災事故でお困りの方、ご家族を亡くされた方、後遺障害でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。