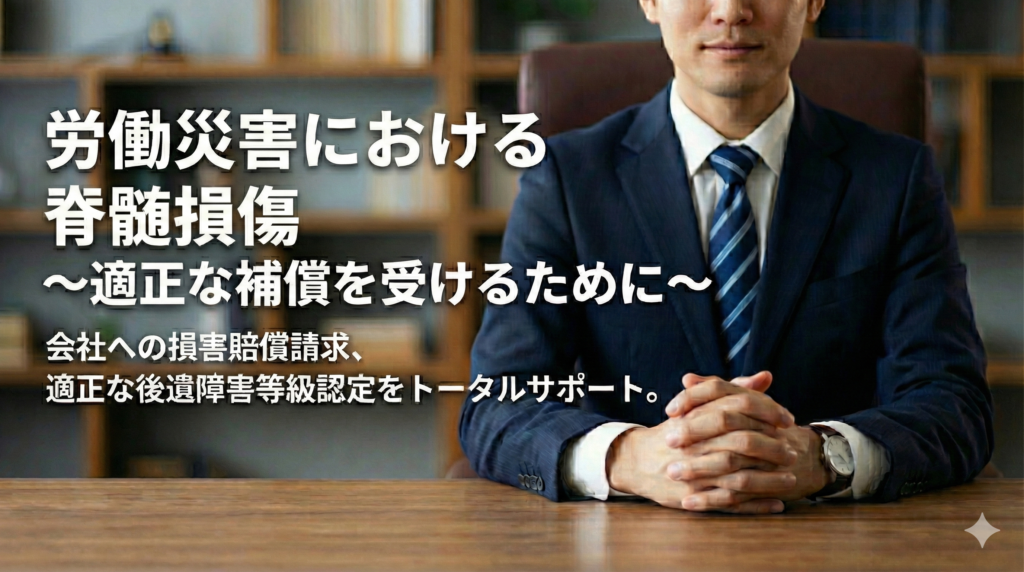
労働災害における脊髄損傷~適正な補償を受けるために~
労災事故で脊髄を損傷してしまうと、それまでの生活が一変してしまいます。手足の自由が奪われ、日常生活に支障をきたすだけでなく、仕事への復帰も難しくなります。「これからの生活はどうなるのだろう」「十分な補償は受けられるのだろうか」。そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
私は弁護士として15年以上にわたり、労災事故の被害に遭われた方々の相談を数多く受けてきました。特に脊髄損傷のケースでは、適切な補償を受けられるかどうかが、その後の生活を大きく左右します。なぜなら、脊髄は一度損傷すると完全な回復は難しく、継続的な治療やリハビリ、場合によっては介護の支援も必要となるためです。
この記事では、脊髄損傷の基礎知識から労災保険における後遺障害認定の仕組み、どのような補償を受けることができるのかについて、解説していきます。
脊髄損傷で悩まれているご本人やご家族の方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
第1章 脊髄損傷の基礎知識
脊髄は、私たちの体の中で最も重要な神経の一つです。小脳から腰の部分まで伸びているこの中枢神経は、脳からの命令を体の各部位に伝えます。手足を動かしたり、痛みや温度を感じたりする、これらの感覚や運動の機能は、すべてこの脊髄を通じて行われています。
脊髄損傷の障害のタイプ
労災事故によって脊髄が損傷を受けると、その部位より下の運動機能や感覚機能に障害が生じます。この障害は大きく二つのタイプに分けられます。
一つは「完全麻痺」です。これは脊髄が完全に損傷された状態で、損傷部位より下の機能が完全に失われてしまいます。例えば、首の部分にある頚髄を損傷した場合、四肢全てが動かなくなってしまう可能性があります。
もう一つは「不完全麻痺」です。こちらは脊髄の一部が損傷した状態で、症状の程度は様々です。軽症の場合は、ある程度の運動機能が残っていることもありますが、重症の場合は、感覚機能だけが残って運動機能が失われることもあります。
損傷部位と現れる症状
脊髄のどの部分が損傷を受けたかによって、現れる症状は大きく異なります。主な例を挙げると:
・頚髄(首の部分)の損傷:四肢の麻痺が起こりやすい
・第2腰髄から上の部分の損傷:下肢全体の麻痺が起こりやすい
・第3仙髄から下の部分の損傷:肛門周囲の感覚障害や尿路障害が起こりやすい
特に注意が必要なのは、脊髄は一度損傷すると完全な回復は極めて困難だということです。そのため、事故直後の適切な治療と、その後の継続的なリハビリテーションが重要になります。また、後遺障害の程度を評価するためには、画像診断・神経学的所見が必要となります。
第2章 後遺障害認定について

脊髄損傷の場合、その後の生活を支える補償を受けるためには、労災保険における後遺障害等級の認定が重要な意味を持ちます。脊髄損傷の場合は主に「神経系統の障害」として認定されます。
脊髄損傷の後遺障害等級は、主に以下のような点から総合的に判断されます。
・麻痺の種類と程度(完全麻痺か不完全麻痺か)
・介護の必要性
・労働能力への影響(どの程度の労働が可能か)
・日常生活動作の制限の程度
・その他の合併症の有無
以下で、後遺障害等級ごとの認定基準について述べます。
・第1級の3の認定
最も重い等級である第1級の3は、「常に介護を要する」状態が認定の重要な基準となります。
具体的には:
・高度の四肢麻痺がある場合
・高度の対麻痺がある場合
・中等度の四肢麻痺があり、食事、入浴、用便、更衣などに常時介護が必要な場合
・中等度の対麻痺があり、食事、入浴、用便、更衣などに常時介護が必要な場合
などが該当します。
・第2級の2の2の認定
第2級の2の2は、「随時介護を要する」状態が基準となります。
・中等度の四肢麻痺がある場合
・軽度の四肢麻痺でも、食事、入浴、用便、更衣などに随時介護が必要な場合
・中等度の対麻痺があり、食事、入浴、用便、更衣などに随時介護が必要な場合
などが該当します。
・第3級の3の認定
第3級の3は、「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができない」状態が基準となります。
・軽度の四肢麻痺がある場合
・中等度の対麻痺
などが該当します。
・第5級の1の2の認定
第5級の1の2は、「きわめて軽易な労務以外の労務に服することができない」状態が基準となります。
・軽度の対麻痺
・一下肢の高度の単麻痺
などが該当します。
・第7級の3の認定
第7級の3は、一下肢の中等度の単麻痺が認められる場合、「軽易な労務以外の労務に服することができない」として認定されます。
・第9級の7の2
第9級の7の2は、一下肢の軽度の単麻痺が認められる場合、「通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制限される」として認定されます。
・第12級の12
第12級の12は、「通常の労務は可能だが、脊髄障害のため、多少の障害を残すもの」が基準となります。
・運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺が残っている
・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められる
などが該当します。
※後遺障害について詳しくはこちら:労災で後遺障害が残ると言われた方へ
第3章 労災事故による脊髄損傷で受けられる補償
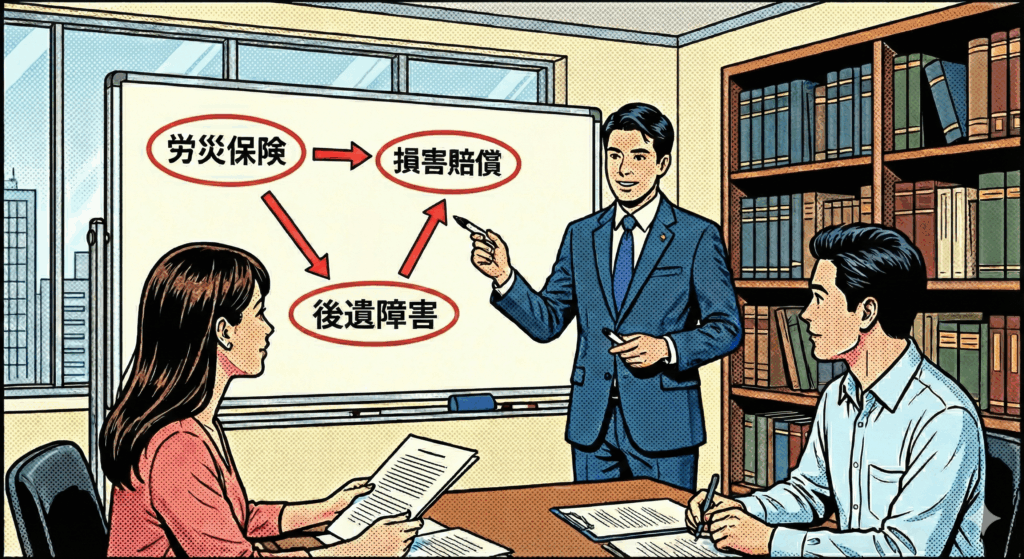
労災事故で脊髄損傷となった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。
労災保険からの給付内容
まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。
療養補償給付
療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。脊髄損傷の場合、治療やリハビリが長期化することも多く、この給付は重要な意味を持ちます。
休業補償給付
休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。
障害補償給付
後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。
介護補償給付
脊髄損傷により、介護が必要と認められる場合には、介護補償給付を受けることができます。
使用者に対する損害賠償請求
労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。
この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害・逸失利益・介護費用の不足分などを請求することができます。
※使用者に対する損害賠償請求については詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ
まとめ:適切な補償を受けるために
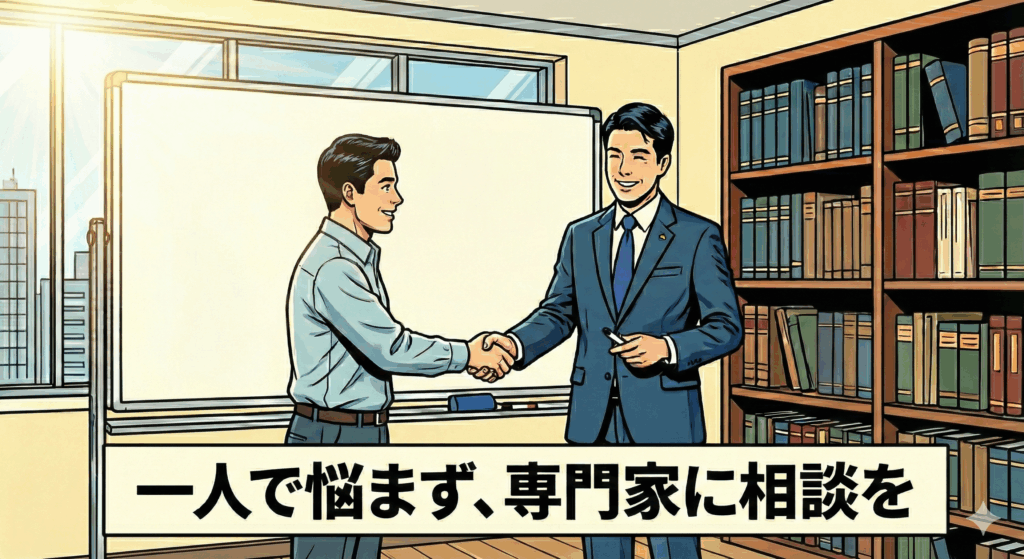
脊髄損傷の補償問題において、最も大切なのは、被害者とそのご家族の生活を守ることです。そのためには、適切な補償を確実に受けることが重要となります。
被害者とそのご家族の方々が、少しでも安心して治療・介護に専念できるよう、私たち弁護士が全力でサポートさせていただきます。一人で悩まず、まずはご相談ください。










