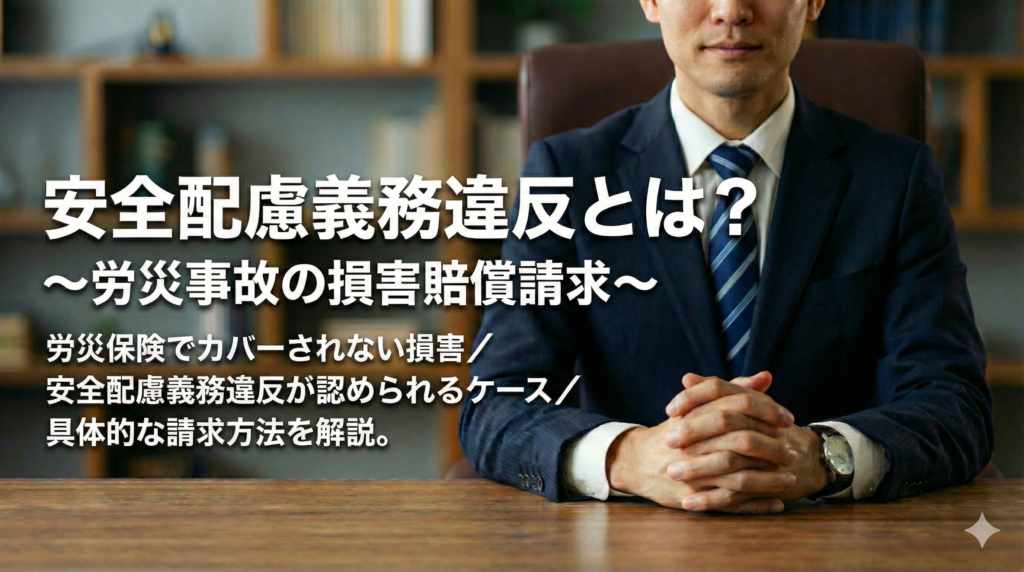
安全配慮義務違反とは?
~労災事故の損害賠償~
労災事故に遭われた方は、さまざまな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
「労災保険の補償だけで十分なのだろうか」
「会社の安全対策に問題があったのでは」
「会社に対して損害賠償を請求することはできるのだろうか」
このような疑問や不安をお持ちの方は少なくありません。実際、私の事務所にも労災事故の被害に遭われた方から、このような相談が数多く寄せられています。
この記事では、労災における安全配慮義務違反について、以下の点を詳しく解説していきます。
・安全配慮義務違反とは何か
・労災保険の補償ではカバーされない損害とは
・安全配慮義務違反が認められるケース
・会社への損害賠償請求の具体的な方法
労災事故によって、心身ともに大変な思いをされている方々に、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思います。
第1章 安全配慮義務違反とは何か
会社に「安全配慮義務違反」が認められる場合、会社に損害賠償を請求することができます。では、安全配慮義務とはどのようなものなのでしょうか。
安全配慮義務の法的根拠
安全配慮義務は、労働契約法や労働安全衛生法によって定められた会社の義務です。
労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。
また、労働安全衛生法第3条第1項においても、会社は法律で定める最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保しなければならないと規定されています。
安全配慮義務の基本的な考え方
安全配慮義務とは、簡単に言えば「労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務」のことです。
この考え方は、労働契約法が制定される以前から、裁判所の判例によって確立されてきました。
※最高裁判所は、ある自衛隊員が車両整備中に事故で死亡した事案において、「労働者の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務」があると判断し、安全配慮義務という考え方を明確に示しています。
会社が負うべき具体的な義務
安全配慮義務の具体的な内容は、それぞれの職場や作業の特性によって異なります。しかし、一般的には以下のような義務が含まれます。
・作業現場の安全性を確保する義務 ・必要な安全設備や保護具を設置・支給する義務 ・作業手順書を作成し、適切な作業方法を指導する義務 ・労働者の健康状態に配慮する義務 ・危険な作業に対する教育・訓練を実施する義務
これらの義務に違反して労災事故が発生した場合、会社には安全配慮義務違反があったと判断される可能性が高くなります。
第2章 労災保険給付だけでは十分ではない?
労災事故に遭われた場合、まず受けられるのが労災保険からの補償です。しかし、この労災保険の補償だけでは、実際に被った損害を十分にカバーできないことがあります。
労災保険から受けられる補償とは
労災保険からは、主に以下のような補償を受けることができます。
【治療費】
まず、治療費については、労災保険から全額が支給される「療養補償給付」があります。これにより、治療費を心配することなく、安心して治療に専念することができます。
【休業補償給付】
また、ケガの治療のために仕事を休まなければならない場合には、給料の約80%が支給される「休業補償給付」(うち20%は労災保険の特別支給金)を受けることができます。
【障害補償給付】
さらに、治療を続けても症状が改善せず、後遺障害が残ってしまった場合には、その障害の程度に応じて「障害補償給付」が支給されます。
労災保険では補償されない損害
しかし、このような労災保険からの補償には限界があります。
まず、休業補償は給与の80%相当額(うち20%は労災保険の特別支給金)に限られます。長期の療養が必要な場合、この収入減は家計に大きな影響を与えかねません。
また、労災事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険からは一切支給されません。入院や通院による苦痛、後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛については、別途、会社に対して損害賠償を請求する必要があるのです。
さらに、後遺障害により労働能力が低下して、将来の収入が減少してしまう「逸失利益」についても、労災保険の障害補償給付では完全には補償されません。障害補償給付は一定の基準で計算された金額が支給されるため、実際の収入の減少分を十分にカバーできないことが多いのです。
損害賠償請求をする理由
このように、この労災保険の補償だけでは、実際に被った損害を十分にカバーできない損害について、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償を請求することを検討しなければなりません。
第3章 具体的にどのような場合に安全配慮義務違反となるのか
安全配慮義務違反が認められるかどうかは、それぞれの業種や作業内容によって判断が異なります。ここでは、代表的な業種における具体例を見ていきましょう。
製造業における安全配慮義務違反
製造業では、工場で機械を操作中に機械に腕を挟まれてしまったというような機械を使用した作業中の事故が多く見られます。
労働安全衛生規則第101条では、機械の危険な部分には「覆いや囲い」等を設置することが義務付けられており、危険な箇所に適切な防護カバーが設置されていなかった場合、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高くなります。
また、以下のような場合も安全配慮義務違反となる可能性があります。
・機械の使用方法について十分な教育訓練を行っていなかった
・危険な作業について作業手順書を作成していなかった
・機械の定期点検や整備を怠っていた
建設業における安全配慮義務違反
建設現場では、高所からの転落事故が深刻な問題となっています。
そのため、労働安全衛生規則519条は、高さ2メートル以上の高所作業における墜落防止措置を義務付けており、高所からの転落事故においては、以下のような例が安全配慮義務違反に当てはまる可能性があります。
・2m以上の高所作業での転落防止措置の不備
・危険な作業指示(荷物を持っての昇降など)
・不適切な器具の使用(天板に乗る、脚立に跨る等)
・不整形地での適切でない脚立の使用
・はしごの固定不備
・器具自体の不具合
運送業における安全配慮義務違反
運送業において、労災事故の多くは荷物の積み下ろしや搬入出時に発生しています。
こうした作業は、トラックの荷台や倉庫内で行われることが多く、フォークリフトや手作業で重い荷物を扱う際に怪我をするリスクが高まります。特に、重い荷物を無理な体勢で持ち上げることによる腰痛や、荷物が落下した際に起こる怪我が一般的です。
このような荷物の積み下ろし作業中の事故防止のために、作業の手順の教育や適切な安全装置の使用などの安全対策が求められいます。そのため、会社はフォークリフトの操作に関する資格取得や、作業現場での安全確認など、労働者が安全に作業を行うための環境整備をする必要があり、これらの安全対策を怠っていた場合、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
第4章 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の進め方
会社に安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償請求をすることができます。
損害賠償請求は、大きく分けて「示談交渉」と「裁判」という2つの方法があります。通常は、まず示談交渉を行い、それでまとまらない場合に裁判という流れになります。
①示談交渉による解決
示談交渉では、労働者側の代理人弁護士が会社側に損害賠償請求の通知書を送付することから始まります。その後、会社側の代理人弁護士との間で交渉を重ねていくのが一般的です。
示談交渉によって解決を図るメリットは以下の点にあります。
・比較的短期間で解決できる
・当事者の精神的負担が少ない
・柔軟な解決が可能
一方で、以下のようなデメリットもあります。
・会社側の対応次第では十分な賠償額を得られない可能性がある
・当事者の合意が必要なため、示談が成立しない可能性がある
②裁判による解決
示談交渉で合意に至らない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。裁判では、会社の安全配慮義務違反の存在や、損害の内容・金額について、証拠に基づいて主張・立証していきます。
裁判のメリットとしては以下の点が挙げられます。
・法的な判断に基づいて適切な賠償額が決定される
・遅延損害金・弁護費用が損害として認められる
・判決によって強制執行が可能
一方で、以下のようなデメリットがあります。
・解決までに1年以上の時間がかかるのが通常
・当事者の精神的負担が大きい
弁護士への相談の重要性
労災事故の損害賠償請求では、安全配慮義務違反の立証や損害額の算定など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。また、示談交渉や裁判の進め方についても、経験と専門知識が求められます。
そのため、損害賠償請求を検討される場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
【まとめ】労災事故の損害賠償請求で大切なこと
ここまで、労災における安全配慮義務違反と損害賠償請求について詳しく見てきました。
最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。
・労災事故が発生した場合、労災保険からの補償を受けることができます。しかし、慰謝料や逸失利益など、労災保険では十分にカバーされない損害も存在します。
・会社に安全配慮義務違反が認められれば、損害賠償請求をすることができます。具体的には、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合や、事故を予見し防止することが可能だったにもかかわらず、必要な対策を講じていなかった場合などが該当します。
・損害賠償請求は、示談交渉や裁判によって行うことができますが、どちらの方法を選択するにせよ、専門的な知識や経験が必要となります。
当事務所では、労災事故の被害に遭われた方の相談を数多く受けてきました。その経験から言えることは、弁護士に相談することで、状況が大きく改善するケースが少なくないということです。
不安や疑問を抱えている方は、まずは無料相談をご利用ください。










