目次
アスベスト給付金申請のポイントについて
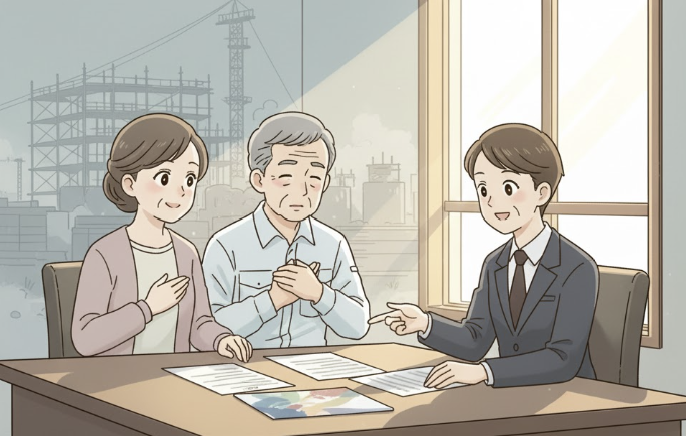
『建設現場で長年働いてきた方が、呼吸器の病気で苦しんでいる。医師からは「間質性肺炎」と診断されたが、アスベストとの関連については何も言われなかった。インターネットでアスベスト給付金について調べてみたものの、「中皮腫や石綿肺といった病名でなければ対象にならない」と書いてあり、申請を諦めてしまった』
『あるいは、家族がアスベスト関連の病気で亡くなったが、勤めていた会社はすでに廃業しており、当時の資料も何も残っていない。労災保険の申請には会社の証明が必要だと聞いて、これも諦めてしまった』
『さらには、家族が亡くなってからすでに数年が経過しており、「もう遅すぎるのではないか」と考えて、給付金の申請をしないまま時間だけが過ぎていく』
このように、本来であれば給付金を受け取れるはずなのに、様々な理由で申請を諦めてしまっている方が数多くいらっしゃいます。しかし、実際には諦める必要がないケースが多いのです。
アスベスト被害は、長年にわたる粉じんへの暴露によって引き起こされる深刻な健康被害です。被害者やそのご家族が、本来受け取れるはずの給付金を受け取れないまま諦めてしまうことは、あまりにも不公平であり、私たち法律家としても見過ごすことはできません。
この記事では、アスベスト給付金の全体像を分かりやすく解説するとともに、「諦めてはいけない理由」について具体的な事例を交えながら詳しくお伝えしていきます。
この記事を最後まで読んでいただければ、アスベスト給付金について正しい知識を得ることができ、諦めずに申請する道筋が見えてくるはずです。アスベスト被害で苦しんでいる方、そしてそのご家族の方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
第1章:アスベストによる五大疾患と知っておくべき救済制度

この章では、アスベスト被害の基礎知識として、対象となる五大疾患と四大救済制度について詳しく解説していきます。
アスベストが原因で発症する五大疾患
アスベスト関連疾患として、現在の給付金制度で対象となっているのは次の5つの疾患です。
中皮腫
中皮腫は、肺を取り囲む胸膜や、肝臓・胃腸などの周囲にある腹膜、心臓を覆う心膜などの表面を覆う「中皮」にできる悪性腫瘍です。アスベストばく露との関連性は非常に高く、代表的なアスベスト関連疾患として知られています。
ただし、中皮腫は確定診断が難しい疾患でもあります。少量・短期間のアスベストばく露でも発症する可能性があるとされており、予後も厳しい病気です。
石綿肺
石綿肺とは、アスベストを大量に吸入したことで、肺が線維化してしまう病気です。線維化とは、肺が硬くなって柔軟性を失ってしまう状態を指します。
石綿肺は、じん肺(塵肺)の一種であり、間質性肺炎及びその悪化した病態である肺線維症の一種でもあります。中皮腫が少量・短期間のアスベストばく露でも発症するのに対し、石綿肺は大量かつ長期間吸入しないと発症しないとされています。
原発性肺がん
原発性肺がんは、気管支あるいは肺胞を覆う上皮に発生する悪性の腫瘍です。中皮腫と異なり、喫煙をはじめとしてアスベスト以外の様々な原因でも発生します。
労災などの制度での累計認定件数は、中皮腫に次いで2位となっています。ただし、一定程度のアスベストばく露があっても、「喫煙などが原因だろう」と思い込んで申請をしていないケースが相当数あると考えられます。
びまん性胸膜肥厚
びまん性胸膜肥厚は、臓側胸膜(肺を覆う膜)が炎症を起こした慢性的な線維性胸膜炎です。石綿肺との合併や、良性石綿胸水の後遺症として生じることが多いとされています。
良性石綿胸水
胸水のうち、石綿粉じんを吸引したことが原因で胸膜炎が発生することにより生じたものを良性石綿胸水と呼びます。
「良性」という言葉がついていますが、これは「悪性腫瘍(がん)ではない」という意味であり、予後が良好なことを意味するわけではありません。労災保険と建設アスベスト給付金制度では対象となりますが、石綿健康被害救済制度では対象外の疾患となる点に注意が必要です。
対象疾病と診断されていなくても諦めてはいけない
ここで重要なのは、上記の五大疾患と診断されていなくても、諦める必要はないという点です。
実際の医療現場では、「間質性肺炎」「肺線維症」「胸膜炎」「肺気腫」「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」「中皮腫疑い」といった病名で診断されているケースが多くあります。しかし、これらの病名であっても、審査機関による審査の結果、最終的に五大疾患だと認定されるケースが数多く存在するのです。
特に「間質性肺炎」や「肺線維症」と診断されている場合は要注意です。後ほど詳しく解説しますが、実は「隠れ石綿肺」であるケースが非常に多いのです。
アスベスト被害者を救済する四大制度
アスベスト被害に対する救済制度は、大きく分けて4つあります。それぞれの制度には対象者や給付内容に違いがあるため、自分がどの制度を利用できるのかを正しく理解することが重要です。
労災保険
労災保険は、労働者及び労災保険の特別加入者を対象とした制度です。対象疾病は、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の五大疾患すべてです。
給付内容は、休業補償給付、療養補償給付、遺族補償給付、葬祭料などがあり、非常に手厚い補償が受けられます。認定基準については、厚生労働省労働基準局長通知「石綿による疾病の認定基準について」に詳しく定められています。
特別遺族給付金
特別遺族給付金は、死亡の翌日から5年以上が経過したことにより遺族補償給付の消滅時効が完成してしまった被災者の遺族を対象とした制度です。
対象疾病は労災保険と同じく五大疾患すべてです。給付内容は、特別遺族年金(遺族1人の場合には年240万円)または特別遺族一時金(1200万円)となっており、認定基準は労災保険に準じます。
石綿健康被害救済制度
石綿健康被害救済制度は、中皮腫、原発性肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚に罹患した者を対象とした制度です。注意すべき点は、良性石綿胸水は対象外となっていることです。
給付内容は、存命(療養)中の場合は医療費と療養手当103,870円/月、死亡の場合は特別遺族弔慰金280万円と特別葬祭料199,900円となっています。認定基準は、石綿健康被害救済法及び中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会「医学的判定に関する留意事項」に定められています。
建設アスベスト給付金制度
建設アスベスト給付金制度は、1972年10月から2004年9月までの間に、一定の建設業務に従事していた者を対象とした制度です。
具体的には、大工、左官、鉄骨工、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督などの職種が該当します。
重要なのは、労働者のみならず、一人親方、一定規模以下の中小事業主、一定規模以下の法人代表者も含まれる点です。
給付内容は、病態に応じて550万円から1300万円となっており、喫煙習慣その他の減額事由がある場合は減額されます。認定基準は、実質的には労災認定基準と同様です。
自分がどの制度を利用できるのか
これら4つの制度のうち、どの制度を利用できるかは、被害者の職業や働き方、疾病の種類によって異なります。
たとえば、建設会社に長年労働者として勤めており、現場作業でアスベストにばく露して肺がんで亡くなった方の場合、①労災保険or石綿健康被害救済制度のいずれか、②建設アスベスト給付金制度が利用可能です。
一方、長年一人親方として働いており、建設現場でアスベストにばく露して良性石綿胸水で入院している方の場合、建設アスベスト給付金制度のみ利用可能となります。ただし、労災保険に特別加入していた場合や、中皮腫など別の病名が診断された場合などは、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用ができることもあります。
また、アスベスト建材が用いられた自宅に住んでいたところ中皮腫を発症して亡くなった方の場合、石綿健康被害救済制度のみ利用可能となります。ただし、短期間であっても若い頃に建設現場でのアルバイトをしていた場合などは、労災保険や建設アスベスト給付金制度の利用ができることもあります。
制度間の併給について
制度間の併給については、注意すべきルールがあります。
労災保険と石綿健康被害救済制度は併給不可となっており、どちらか片方からしか受け取れません。一方、労災保険or石綿健康被害救済制度と、建設アスベスト給付金制度は併給可能であり、両方から受け取れます。
この併給のルールを理解した上で、どの制度から優先的に申請すべきかを判断することが重要です。次の章では、なぜ労災保険を最優先で申請すべきなのか、その理由について詳しく解説していきます。
第2章:なぜ労災保険から申請するのが最も有利なのか
前章で解説したとおり、アスベスト被害者を救済する制度は複数存在します。では、複数の制度を利用できる場合、どの制度から申請すべきなのでしょうか。
結論から言えば、労災保険(特別遺族給付金を含む)を最優先で申請すべきです。この章では、その理由について詳しく解説していきます。
アスベスト給付金制度の優先順位
アスベスト給付金制度を利用する際の優先順位は、次のとおりです。
第一に労災保険(または特別遺族給付金)、第二に石綿健康被害救済制度、第三に建設アスベスト給付金制度という順番になります。
この優先順位は、単なる申請の順番というだけではなく、被害者にとって最も有利な結果を得るための順序でもあります。特に労災保険を最優先で申請することには、大きな意味があるのです。
労災保険を最優先で申請すべき4つの理由
労災保険を最優先で申請すべき理由は、大きく分けて4つあります。
理由1:補償金額が極めて手厚い
労災保険の補償金額は、他の制度と比較して極めて手厚いものとなっています。
石綿健康被害救済制度の場合、存命中は医療費と月額103,870円の療養手当、死亡の場合は特別遺族弔慰金280万円と特別葬祭料199,900円が支給されます。建設アスベスト給付金制度の場合は、病態に応じて550万円から1300万円の一時金が支給されます。
これに対し、労災保険では休業補償給付、療養補償給付、遺族補償給付、葬祭料など、様々な給付が長期間にわたって支給されます。
たとえば、遺族補償給付は年金形式で支給されるため、トータルの補償額は他の制度と比べて大幅に高額になります。遺族補償年金の場合、遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分が毎年支給されます。給付基礎日額が1万円の場合、年間153万円から245万円が支給され続けることになります。これは石綿健康被害救済制度の一時金280万円と比較しても、長期的には大きな差となります。
理由2:認定基準が被害者に有利
労災保険の認定基準は、他の制度と比較して被害者に有利な内容となっています。
特に重要なのは、労災保険では「業務起因性」の判断において、かなり柔軟な運用がなされている点です。アスベストばく露作業への従事期間や胸膜プラークの有無など、一定の要件を満たせば、比較的認定されやすい基準が設けられています。
また、石綿健康被害救済制度では対象外となっている良性石綿胸水も、労災保険では対象疾病となっています。このように、対象範囲の広さという点でも労災保険は有利です。
理由3:認定の運用が柔軟かつ被害者に有利
労災保険の認定実務においては、認定基準の運用が柔軟かつ被害者に有利に行われています。
たとえば、医療機関で明確に五大疾患と診断されていない場合でも、労働基準監督署が労災医員の意見を聴取し、その結果として対象疾病に該当すると判断されるケースが多くあります。「間質性肺炎」と診断されていた方が、労災医員の意見によって「石綿肺」と認定されたケースは、決して珍しくありません。
また、アスベストばく露作業への従事を証明する資料が不十分な場合でも、労働基準監督署が職権で調査を行い、認定に至るケースもあります。このような柔軟な運用は、被害者救済の観点から非常に重要です。
理由4:労災保険の認定がその後に及ぼす大きな影響
労災保険で認定されることは、その後の他の制度の申請にも大きな影響を及ぼします。
労災保険で認定されれば、建設アスベスト給付金制度の申請において、業務上のアスベストばく露や対象疾病への罹患が既に認められていることになります。これにより、建設アスベスト給付金制度の申請がスムーズに進む可能性が高まります。
また、労災保険の認定があれば、それ自体が客観的な証拠となり、被害者やその家族の精神的な負担も軽減されます。「本当にアスベストが原因だったのか」という不安や疑問が解消され、安心して治療や生活に専念できるようになります。
労災保険申請の具体的な流れ
労災保険の申請は、労働基準監督署に対して行います。
申請には、労災保険請求書のほか、医師の診断書、アスベストばく露作業への従事を証明する資料などが必要となります。事業主の証明欄がありますが、事業主が廃業している場合や証明を拒否する場合でも、その旨を説明する文書を添付すれば申請は受け付けられます。
申請後、労働基準監督署が調査を行い、必要に応じて労災医員の意見を聴取します。審査期間は案件によって異なりますが、最低でも6か月程度はかかると考えておくべきです。
認定されれば、各種給付が開始されます。不支給決定がなされた場合でも、審査請求や再審査請求といった不服申立ての手続きを取ることができます。
まずは労災保険の申請から始めよう
アスベスト被害で苦しんでいる方、またはそのご家族は、まず労災保険の申請を検討すべきです。
「自分は労働者ではなかったから」「会社が廃業しているから」「もう時間が経ちすぎているから」といった理由で諦める必要はありません。労災保険の対象となる可能性は、皆さんが思っている以上に広いのです。
次の章では、給付金認定のカギを握る重要な医学的所見である「胸膜プラーク」について詳しく解説していきます。この知識を持っているかどうかが、認定の可否を左右することもあるため、ぜひ理解を深めていただきたいと思います。
第3章:給付金認定のカギを握る「胸膜プラーク」
アスベスト給付金の認定において、重要な医学的所見の一つが「胸膜プラーク」です。この胸膜プラークの有無や程度が、認定の可否を決定的に左右することがあります。
しかし、胸膜プラークという言葉を初めて聞く方も多いでしょうし、医師から説明を受けていないケースも少なくありません。この章では、胸膜プラークとは何か、なぜ重要なのか、そして認定基準においてどのように扱われているのかについて詳しく解説していきます。
胸膜プラークとは何か
胸膜プラークとは、アスベストを吸ったことにより、数十年後に肺を覆う膜(胸膜)にできる白い板状の肥厚班のことです。厚さは1mmから10mm程度で、胸部レントゲン写真やCT画像で確認することができます。
重要なのは、胸膜プラーク自体は癌化することはなく、治療を要するようなものではないという点です。つまり、胸膜プラークがあること自体が病気というわけではありません。
しかし、胸膜プラークの存在は、その人が過去にアスベストにばく露したことを示す重要な証拠となります。アスベスト関連疾患に特徴的な画像所見であり、各制度の認定基準にも用いられているのです。
なぜ胸膜プラークが重要なのか
胸膜プラークが重要な理由は、それがアスベストばく露の客観的な証拠となるからです。
アスベスト給付金の認定においては、対象疾病に罹患していることだけでなく、その疾病がアスベストばく露によって引き起こされたことを証明する必要があります。しかし、アスベストばく露から発症までには数十年という長い潜伏期間があるため、ばく露の事実を証明することは容易ではありません。
そこで重要になるのが胸膜プラークです。胸膜プラークが認められれば、その人が過去にアスベストにばく露したことが医学的に証明されます。これにより、認定のハードルが大きく下がるのです。
特に原発性肺がんの場合、胸膜プラークの有無及び程度が認定に決定的な影響を及ぼします。また、石綿肺についても、医学的診査の際に石綿肺か否かを裏付ける根拠の一つとして、胸膜プラークの有無及び程度が用いられています。
肺がん認定における胸膜プラークの役割
原発性肺がんの労災認定基準において、胸膜プラークは重要な位置を占めています。
労災認定基準では、医療画像によって胸膜プラークが認められ、かつ石綿ばく露作業への従事期間が10年以上ある場合、原発性肺がんは労災認定されると定めています。
さらに注目すべきは、「顕著な胸膜プラーク」が認められる場合です。顕著な胸膜プラークが認められ、かつ石綿ばく露作業への従事期間が1年以上ある場合、原発性肺がんは労災認定されます。
つまり、顕著な胸膜プラークがあれば、わずか1年の従事期間でも認定される可能性があるのです。これは、胸膜プラークの程度がいかに重要かを示しています。
「顕著な胸膜プラーク」とは
では、「顕著な胸膜プラーク」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
認定基準では、次の2つのパターンのいずれかに該当する場合を「顕著な胸膜プラーク」としています。
1つ目のパターンは、胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ胸部CT画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるものです。
具体的には、両側又は片側の横隔膜に太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を伴わない場合、あるいは両側側胸壁の第6から第10肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わない場合が該当します。
2つ目のパターンは、胸部CT画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部CT画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の4分の1以上のものです。
これらの基準は専門的で分かりにくいかもしれませんが、要するに胸部レントゲンやCT画像で一定程度以上の胸膜プラークが確認できれば、「顕著な胸膜プラーク」と判断されるということです。
胸膜プラークがなくても認定される可能性はある
ここまで胸膜プラークの重要性を強調してきましたが、胸膜プラークが見つからなければ認定されないというわけではありません。
各対象疾病には、胸膜プラークを指標としたもの以外の認定基準も存在します。たとえば、原発性肺がんであれば、石綿肺の所見があれば労災認定されます。具体的には、胸部レントゲン写真でじん肺法に定める第1型以上の石綿肺所見が認められる場合です。
また、中皮腫の場合は、基本的に中皮腫と診断されれば、胸膜プラークの有無にかかわらず労災認定されます。中皮腫自体がアスベストばく露との関連性が極めて高い疾患だからです。
びまん性胸膜肥厚や良性石綿胸水についても、それぞれ独自の認定基準が設けられており、必ずしも胸膜プラークが必要というわけではありません。
医療画像の確認が重要
胸膜プラークの有無を確認するためには、医療画像を詳細にチェックすることが重要です。
主治医が胸膜プラークについて何も言及していない場合でも、それは胸膜プラークがないことを意味するわけではありません。主治医は治療に専念しているため、労災認定のための所見まで詳しく検討していないことが多いのです。
したがって、アスベスト給付金の申請を検討する際には、改めて医療画像を確認し、胸膜プラークの有無を専門的に判断する必要があります。これは、アスベスト被害に詳しい弁護士や医師に依頼することをお勧めします。
特に、過去に撮影された胸部CT画像がある場合は、それらすべてを確認すべきです。胸膜プラークは経年的に変化することがあり、古い画像の方がはっきり写っている場合もあるからです。
第4章:諦めてはいけない3つのケース
アスベスト給付金の申請を検討している方の中には、様々な理由で「自分は対象外だろう」と諦めてしまっている方が数多くいらっしゃいます。しかし、実際には諦める必要がないケースが非常に多いのです。
この章では、特に多い3つの諦めパターンについて、それでも申請できる理由と方法を、実際の事例を交えながら詳しく解説していきます。
ケース1:対象疾病と診断されていない場合
最も多い諦めパターンの一つが、「対象疾病と診断されていないから申請できない」というものです。
たとえば、医師から「間質性肺炎」と診断された方が、アスベスト給付金について調べたところ、対象疾病は中皮腫、石綿肺、原発性肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の5つだと知り、「自分は石綿肺ではなく間質性肺炎だから対象外だ」と判断してしまうケースです。
しかし、これは大きな誤解です。対象疾病が明確に診断されていなくても、審査機関による審査の結果、対象疾病に罹患していたと認定されるケースがしばしばあるのです。
なぜ石綿肺が「間質性肺炎」と診断されやすいのか
石綿肺が「間質性肺炎」や「肺線維症」とだけ診断されやすい理由は、石綿肺が間質性肺炎の一種であり、かつ間質性肺炎の発症原因を特定(鑑別)することが一般に困難であるためです。
間質性肺炎には様々な原因があります。じん肺の一種として、ケイ肺、混合粉じん性じん肺、石綿肺、炭鉱夫じん肺、溶接工肺などがあります。また、じん肺以外にも、ウイルス性のもの、膠原病性のもの、動物の毛由来のもの、特発性(原因不明)のものなど、多岐にわたります。
主治医は、患者の治療に専念しているため、間質性肺炎の原因がアスベストなのか他の要因なのかを詳しく鑑別していないことが多いのです。そのため、「間質性肺炎」という病名だけで診断が終わってしまうケースが少なくありません。
「隠れ石綿肺」のケースが非常に多い
実際の現場では、「隠れ石綿肺」のケースが非常に多く存在します。
間質性肺炎や肺線維症と診断されている方の中には、実は石綿肺である方が相当数いると考えられます。特に、建設業や造船業など、アスベストばく露の可能性が高い職業に長年従事していた方の場合、その可能性はさらに高まります。
したがって、「間質性肺炎」「肺線維症」「肺気腫」「COPD」「胸膜炎」といった病名で診断されている場合は、特に注意が必要です。これらの病名であっても、労災保険などを申請すれば、審査の過程で石綿肺やその他の対象疾病と認定される可能性があるのです。
ケース2:会社がなくなっている場合
2つ目の諦めパターンは、「勤務先の会社がなくなっているから申請できない」というものです。
零細の建設会社や個人事業主に雇われていた方の場合、現在その会社が存続しているのかどうかも分からない、仮に存続していても社長は代変わりしてしまっていて就労を証明してくれないかもしれない、当時の上司や同僚も連絡先が変わってしまっているか亡くなってしまった、といった状況に直面することがあります。
このような場合、「労働者としての業務上アスベストばく露の立証は無理だから、労災保険申請は諦めよう」と考えてしまう方が多いのです。
しかし、これも諦める必要はありません。会社が廃業していても、あるいは会社が協力してくれなくても、労災保険の申請は可能なのです。
年金記録が立証のスタートライン
労災保険適用のための労働者性立証・業務上アスベストばく露立証のスタートラインは、年金の被保険者記録照会回答票です。
年金記録には、過去にどの会社に勤めていたか、いつからいつまで厚生年金に加入していたかが記録されています。この記録によって、過去の勤務先を確認することができます。
年金記録は、最寄りの年金事務所で取得できます。本人が亡くなっている場合は、遺族が取得することも可能です。まずは年金記録を取得し、過去の勤務先を確認することから始めましょう。
年金記録がない場合の対処法
年金記録を取得してみたものの、全期間国民年金だった、あるいはそもそも昔は年金に入っていなかった、というケースもあります。
このような場合でも、諦める必要はありません。年金記録以外にも、就労を証明する資料は様々あります。
具体的には、写真(現場写真、社員旅行などの記念写真)、年賀状、社員名簿や住所録、古い通帳による給与入金記帳などです。これらの資料を丁寧に集めることで、労働者性を立証できる可能性があります。
特に写真は有力な証拠となります。会社の社長や同僚と一緒に写っている写真があれば、その会社で働いていたことを示す重要な証拠になります。また、現場での作業風景を撮影した写真があれば、どのような作業に従事していたかを示す証拠にもなります。
会社が協力しなくても申請は可能
会社が廃業していても、あるいは会社が「労働者ではない」と主張してきても、様々な資料を集めることで労働者性を立証できる可能性があります。
諦めずに、過去の資料を丁寧に探してみることが重要です。実家の押し入れや物置に、古い給料明細や写真が残っているかもしれません。また、当時の同僚や知人に連絡を取ってみることも有効です。
会社が協力してくれないからといって、労災保険の申請を諦める必要はまったくないのです。
ケース3:亡くなってから時間が経っている場合
3つ目の諦めパターンは、「亡くなってから時間が経っているから申請できない」というものです。
労災保険の遺族補償給付には、被災労働者が死亡した日の翌日から5年という消滅時効があります。したがって、死亡から5年以上が経過している場合、通常の労災保険は時効により請求できなくなります。
また、医療機関の医療記録の保存期間は、最後の入通院から5年とされています。したがって、死亡から時間が経っている場合、医療記録が破棄されているのではないか、あるいは保管していても開示してもらえないのではないか、という懸念があります。
このような理由から、「もう遅すぎる」と諦めてしまう方が多いのです。
特別遺族給付金という救済制度
しかし、労災保険の消滅時効が完成してしまった場合でも、特別遺族給付金という救済制度があります。
特別遺族給付金は、死亡の翌日から5年以上が経過したことにより遺族補償給付の消滅時効が完成してしまった被災者の遺族を対象とした制度です。給付内容は、特別遺族年金(遺族1人の場合には年240万円)または特別遺族一時金(1200万円)となっています。
重要なのは、特別遺族給付金は令和14年(2032年)3月27日まで請求可能だという点です。つまり、現時点で死亡から5年以上が経過していても、2032年3月27日までであれば請求できるのです。
したがって、「もう5年以上経っているから無理だ」と諦める必要はありません。特別遺族給付金の申請を検討すべきです。
医療記録の保存期間を過ぎていても諦めない
医療記録の保存期間については、確かに法令上は5年とされています。しかし、実際には病院がそれよりも長く保存していることがしばしば見受けられます。
10年以上となると厳しい場合もありますが、保存期間を多少過ぎている程度であれば、現に医療機関が医療記録を保存している可能性は十分にあります。
また、保存期間の経過とは無関係に、現に医療機関が医療記録を保存しているのであれば、遺族に対し開示しなくてはならないと考えられます。個人情報保護の観点からも、本人が亡くなっている場合、遺族には開示請求権があるとされているのです。
さらに、労災保険申請後、労働基準監督署からの開示要請であれば応じる病院もあります。遺族からの直接の開示請求には応じなかった病院が、労働基準監督署からの要請には応じるというケースは珍しくありません。
時間が経っていても諦めずに相談を
亡くなってから時間が経っているという理由だけで諦めるのは、あまりにももったいないことです。
特別遺族給付金という救済制度がある以上、2032年3月27日までは請求のチャンスがあります。また、医療記録についても、取得できる可能性は残されています。
時間が経っているからこそ、一日も早く専門家に相談し、申請の準備を始めることが重要です。時間が経てば経つほど、証拠資料の収集は難しくなっていきます。今すぐ行動を起こすことが、給付金を受け取れるかどうかの分かれ目になるのです。
諦めずに専門家に相談することの重要性
この章で紹介した3つのケースは、いずれも「諦めてしまいがちだが、実は諦める必要がない」典型例です。
対象疾病と診断されていない、会社がなくなっている、亡くなってから時間が経っている、といった状況は、確かに申請のハードルを高くする要因ではあります。しかし、それらは決して申請を不可能にする要因ではありません。
適切な方法で証拠を集め、専門的な知識に基づいて申請を進めれば、給付金を受け取れる可能性は十分にあるのです。
まとめ

ここまで、アスベスト給付金について、申請の全体像から具体的な認定のポイント、諦めてはいけないケースまで詳しく解説してきました。
アスベスト給付金申請で最も大切なこと
アスベスト給付金申請において最も大切なことは、諦めないことです。
この記事を通じてお伝えしてきたように、「自分は対象外だろう」と思っていても、実際には申請できるケースが数多くあります。対象疾病と診断されていない、会社がなくなっている、時間が経っている、といった理由は、いずれも申請を不可能にする要因ではありません。
アスベスト被害は、国の規制が不十分だった時代に、知らないうちにアスベストにばく露させられた結果です。被害者やそのご家族には何の落ち度もありません。適切な補償を受けることは、正当な権利なのです。
その権利を行使するためには、正しい知識を持ち、適切な方法で申請を進めることが重要です。一人で悩んだり、誤った情報に基づいて諦めたりするのではなく、専門家のサポートを受けながら、確実に給付金を受け取る道を進んでいただきたいと思います。
今すぐ行動を起こしてください
アスベスト給付金の申請を検討されている方、あるいは諦めかけている方は、今すぐ行動を起こしてください。
時間が経てば経つほど、証拠資料の収集は難しくなります。関係者の記憶も薄れていきますし、資料も散逸していきます。また、病状が進行してからでは、必要な検査を受けることが困難になる可能性もあります。
まずは、専門家である弁護士に相談することから始めましょう。相談することで、自分のケースが申請可能なのかどうか、どのような資料が必要なのか、どのように進めればいいのかが明確になります。
当事務所では、アスベスト給付金に関する初回相談を受け付けています。
「自分は対象外かもしれない」「証拠が何もない」「もう遅すぎるかもしれない」といった不安や疑問を抱えている方こそ、ぜひ一度ご相談ください。あなたが思っている以上に、申請できる可能性は高いかもしれません。
アスベスト被害で苦しんでいる方、そしてそのご家族が、本来受け取れるはずの給付金を確実に受け取れるよう、私たちは全力でサポートいたします。
一人で悩まず、諦めず、まずは専門家に相談してください。それが、適切な補償を受けるための第一歩です。
あなたとご家族の未来のために、今すぐ行動を起こしましょう。
参考文献
※本記事作成のための参考文献:アスベスト給付金申請ハンドブック・小林 玲生起 (著)・中央経済社











