目次
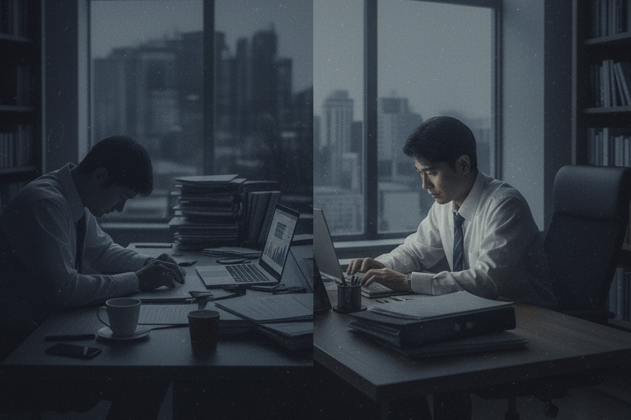
過労死の労災認定基準とは【弁護士が解説】
突然発生する、脳卒中や心筋梗塞といった脳・心臓疾患。もし、それが仕事中に、あるいは過酷な労働が原因で起きてしまったとしたら、ご本人もご家族も、大変な状況におられることと存じます。
過労によって命を落とす「過労死」は、決して他人事ではなく、現代社会において深刻な社会問題となっています。
今後の生活への不安はもちろん、「仕事が原因だったのでは?」という疑問をお持ちかもしれません。実は、仕事が原因で脳・心臓疾患等を発症した場合は、労災として認定される可能性があります。
さらに、会社の安全配慮が不十分だった場合には、会社に対して損害賠償を請求できるケースもあります。
この記事では、過労死が社会問題となっている現代において、仕事中の脳・心臓疾患について、労災認定のポイントや、会社への損害賠償の可能性について、弁護士の視点から詳しく解説いたします。
第1章 過労死とは何か?
過労死とは、業務による強い負荷や長時間労働の結果として、脳・心臓疾患などを発症し、死亡に至ることを指します。代表的なものには、脳出血・くも膜下出血・心筋梗塞・狭心症などがあります。
労災認定の対象となる疾患
過労死で労災認定を受けるためには、まず対象となる以下のような疾患を発症していることが前提となります。
脳疾患では、脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症が該当します。
心疾患では、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤が対象となります。
第2章 過労死の労災認定を受けるための3つの条件
過労死が労災として認定されるためには、厚生労働省が定める「過重負荷(過重労働)」があったと認められる必要があります。具体的には、以下の3つのうちいずれかの条件を満たすことが重要です。
1 異常な出来事
発症直前から前日までの間に、精神的・身体的に極度の負荷を与える突発的または予測困難な異常な事態があったことです。
具体的な例としては、重大事故への遭遇、極度の恐怖体験、生命の危険を感じるような突発的な事故、極度の緊張・興奮・恐怖を伴う事態に遭遇した場合などが挙げられます。
2 短期間の過重業務
発症前おおむね1週間に、日常業務と比較して特に過重な業務に従事したことです。
「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいいます。たとえば、通常では考えられないような連続勤務、急なトラブル対応での徹夜作業、休日が与えられない連続勤務などが該当します。
業務の過重性を評価する際には、労働時間だけでなく、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務、交代制勤務、深夜勤務、作業環境(温度環境、騒音、時差)、精神的緊張を伴う業務なども総合的に考慮されます。
3 長期間の過重業務
発症前おおむね6ヶ月間に、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に従事したことです。
特に重要な基準となるのが労働時間で、発症前1ヶ月間に100時間超、または発症前2~6ヶ月間平均で月80時間超の時間外労働は、過重性の強い要因と評価されます。これがいわゆる「過労死ライン」と呼ばれるものです。
ただし、労働時間だけでなく、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多さ、精神的緊張を伴う業務、作業環境なども総合的に考慮して判断されます。労働時間がより長ければ他の負荷要因がより小さくても業務と発症との関連性が強い場合があり、逆に他の負荷要因がより大きければ労働時間がより短くても関連性が強いと判断される場合があります。
第3章 労災認定のために必要な証拠収集
過労死の労災認定を受けるためには、業務と発症との因果関係を客観的な証拠によって立証することが不可欠です。特に長期間の過重業務を証明するためには、被災労働者がどれだけの時間働いていたのかを明らかにする必要があります。
労働時間の立証が重要
労働時間とは、「使用者の指揮監督下に置かれている時間」をいい、労働からの解放が保障されていない時間も労働時間になります。そのため、会社から休憩時間と指定されていた時間であっても、実際に仕事をしていた場合には、労働からの解放が保障されていないので、労働時間として認められます。
過労死事件では、長期間の過重業務として、被災労働者が発症前1ヶ月間におおむね100時間、または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働をしたことを証明する必要があるため、労働時間の立証が重要になります。
収集すべき証拠の種類
労働時間を立証するための証拠としては、以下のものが挙げられます。
会社が管理している記録
タイムカードや出勤簿は、最も基本的で重要な証拠です。入退館・入退室記録も、実際の在社時間を示す重要な資料となります。
残業申請書は、会社が把握していた残業時間を示すものですが、実際の労働時間との乖離がある場合も多いため、他の証拠と併せて検討する必要があります。
会社で業務上使用していたパソコンのログイン・ログオフ記録は、実際の業務開始・終了時間を客観的に示す非常に有力な証拠です。
賃金台帳や給料明細も、支払われた残業代から逆算して労働時間を推定する際の参考となります。
業務の実態を示す記録
メールの送受信記録は、深夜や早朝の業務実態を示す重要な証拠となります。送信時刻や受信時刻から、実際に業務を行っていた時間を立証できます。
シフト表やスケジュール表、業務日報、出張報告書なども、業務の実態や労働時間を示す資料として有効です。
運送業の方の場合は、タコグラフ(運行記録計)が重要な証拠となります。
個人で作成・保管している記録
労働者個人の携帯電話の発着信・メール送受信記録も、業務に関連する連絡の時間から労働時間を推定する材料となります。
日記、メモ、書き込みのあるカレンダーなど、日常的に記録していたものも貴重な証拠となります。特に、毎日の出勤・退勤時間や業務内容を記録していた場合には、有力な証拠となります。
同僚の証言も重要
労働時間を示す書面がない場合や、書面だけでは不十分な場合には、同僚の証言も重要な証拠となります。一緒に働いていた同僚が、被災労働者の実際の労働状況について証言することで、労働時間の立証を補強できます。ただし、同僚も同じ会社に勤務している場合が多く、会社との関係で証言を控える場合もあるため、早期に協力を求めることが重要です。
医学的証拠の重要性
労働時間の立証と併せて、医学的な証拠も重要となります。
発症時の医師の診断書、救急搬送時の記録、入院カルテなどは、発症の時期や症状の程度を示す重要な証拠です。
また、発症前の健康状態を示す健康診断結果なども、業務と発症との因果関係を判断する際の参考となります。
労災認定は、これらの様々な証拠を総合的に検討して判断されるため、可能な限り多くの客観的な証拠を収集することが重要です。証拠収集には専門的な知識と経験が必要となりますので、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
第4章 労災認定後に受けられる補償と給付
過労死が労災として認定された場合、労災保険から様々な給付を受けることができます。労働者が死亡した場合と、生存しているが後遺障害が残った場合で給付内容が異なりますので、それぞれについて詳しく説明いたします。
労働者が死亡した場合の給付
葬祭料
葬祭料として、「315,000円と給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のどちらか多い方の金額が支給されます。
遺族補償給付
遺族に対して年金または一時金が支給されます。遺族が労働者によって扶養されていた場合には年金として、それ以外の場合には一時金となります。
年金の場合には、遺族の人数に応じて労働者の年収の43%~67%程度が支給されます。一時金の場合には、労働者の年収の3年分程度の金額が支給されます。
具体例として、年収が584万円(給付基礎日額が16,000円)、年間賞与が76万円、ご遺族が妻と子供2人の場合を見てみましょう。
・遺族特別支給金:300万円(定額)
・遺族補償年金:16,000円×223日分(ご遺族3人)=356万8,000円(年額)
・遺族特別年金:2,000円×223日分(ご遺族3人)=44万6,000円(年額)
+子どもの労災就学援護費
第5章 労災保険だけでは足りない?会社への損害賠償請求
労災保険からの給付は、被災された労働者の生活を支える重要な制度ですが、精神的な苦痛に対する慰謝料などは基本的に含まれません。
もし、会社が労働者の健康や安全を守るための配慮(安全配慮義務)を怠った結果、脳・心臓疾患を発症したと認められる場合には、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
安全配慮義務違反とは
労働契約法第5条では、会社には労働者の生命・健康を守る「安全配慮義務」があるとされています。具体的には、会社は労働者の業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負っています。
そのため、会社は労働者が長時間労働によって健康を害さないように、タイムカードなどを用いて労働時間を適正に管理し、働き過ぎの労働者に対しては、勤務を軽減するなどして労働者の疲労が蓄積することがないように配慮しなければなりません。
過労死に至った背景に、明らかに無理な労働を強いた事実や、適切な労働時間管理を怠った事実等があれば、会社の安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を追及できます。
請求できる損害の内容
会社への損害賠償請求では、労災保険ではカバーされない以下のような損害を請求できる可能性があります。
過労死の場合
・葬儀費用:労災保険と同様に葬儀費用を請求できます。
・死亡逸失利益:労働者が死亡したことによって得られなくなってしまった将来の収入のことです。
・死亡慰謝料:労災保険では「慰謝料」は支払われませんが、会社の過失によって労働者が死亡したときには、2,000~2,800万円程度の死亡慰謝料を請求できます。
まとめ:早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方は一度、ご相談ください。
ご相談の予約は、電話でもメールでもLINEでも可能です。
初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらです。











