目次

労災で後遺障害が残ると言われた方へ
労災事故で負った怪我の治療を続けていたところ、主治医から「後遺障害が残るかもしれない」と言われてしまった。そのような状況に置かれた方は、きっと大きな不安を抱えていることでしょう。
「後遺障害って具体的にどういうことなのか」
「今後どのような手続きが必要になるのか」
「労災保険からどの程度の補償を受けられるのか」
など、初めて経験することばかりで、何から手をつけていいのかわからないのではないでしょうか。
私は福井県福井市で弁護士として15年間以上活動し、これまで数多くの労災被害者の方々の後遺障害等級認定をサポートしてまいりました。その経験の中で痛感するのは、後遺障害の等級認定は、被害者の方の人生を大きく左右する重要な手続きだということです。
実際に、等級が1つ違うだけで、労災保険から支給される補償金が100万円以上も変わってしまうケースは珍しくありません。しかし、適切な知識と準備があれば、正当な等級認定を受けて、しっかりとした補償を得ることができるのです。
今回の記事では、労災の後遺障害について、その基本的な仕組みから等級認定の手続き、そして適正な認定を受けるためのポイントまで、わかりやすく解説していきます。不安な気持ちを抱えている方に、少しでも安心と道筋を示すことができれば幸いです。
第1章 労災の後遺障害とは何か
労災事故でけがを負い、治療を続けていても、現在の医学では症状がこれ以上改善しない状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といいます。
症状固定とは、治療を継続しても症状の回復が見込めない状態のことで、原則、主治医によって判断されます。そして、症状固定の時点で残っている症状が「後遺障害」です。
つまり、労災事故が発生する前と比較して、労働者にとって悪い症状が残っており、以前と同じように働くことが困難な状態になっていることを後遺障害といいます。
後遺障害は、手や足の欠損といった重篤なものだけではありません。痛みやしびれが残る、関節の動きが制限される、といった症状も立派な後遺障害の一つです。
症状固定となった場合、原則として労災保険からの治療費の負担は終了します。しかし、後遺障害が残ったことによる労働能力の低下や将来への不安に対しては、労災保険から別の形での補償を受けることができるのです。
その補償を受けるために必要となるのが、労災保険における後遺障害等級認定の申請手続きです。この認定を受けることで、後遺障害の程度に応じた給付金を受け取ることができるようになります。
第2章 後遺障害等級認定の重要性
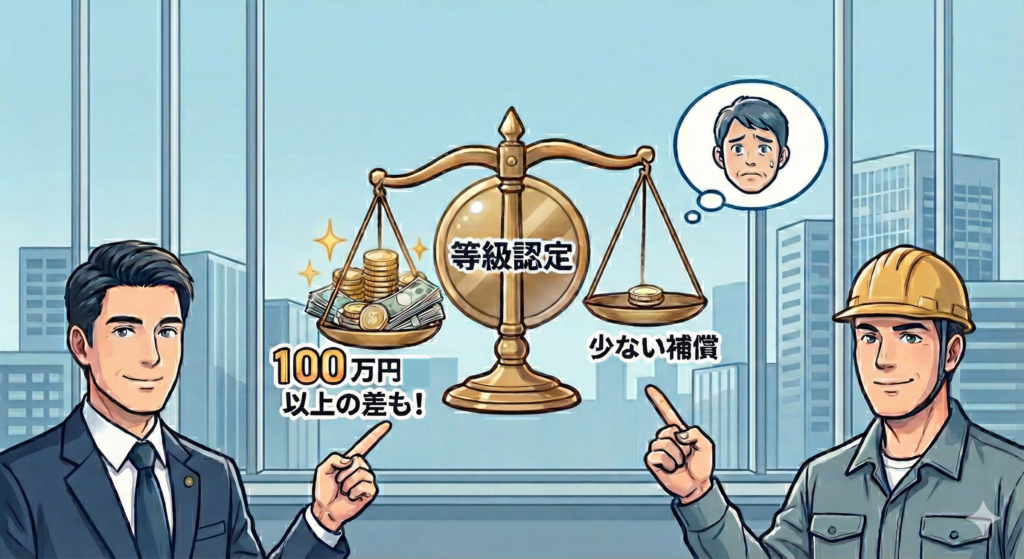
後遺障害が残ると、通常、労働者の労働能力が低下します。労働能力が低下すれば、以前と同じように働くことが困難となり、収入が減少してしまいます。
後遺障害によって労働能力が低下することによる収入の減少に対する補償として、労災保険の障害補償給付があります。この障害補償給付は、後遺障害の等級によって支給される補償金額が決まる仕組みになっています。
後遺障害の等級は、重い方の1級から軽い方の14級まで設定されています。1級から7級までは障害補償年金が支給され、2か月に1回、継続的に労災保険から年金が支給されます。8級から14級までは障害補償一時金が支給され、労災保険から一度だけまとまった補償金が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円の場合、8級から14級までの障害補償一時金は次のように計算されます。
| 等級 | 補償金額 | 計算式 |
| 8級 | 5,030,000円 | 10,000円×503日分=5,030,000円 |
| 9級 | 3,910,000円 | 10,000円×391日分=3,910,000円 |
| 10級 | 3,020,000円 | 10,000円×302日分=3,020,000円 |
| 11級 | 2,230,000円 | 10,000円×223日分=2,230,000円 |
| 12級 | 1,560,000円 | 10,000円×156日分=1,560,000円 |
| 13級 | 1,010,000円 | 10,000円×101日分=1,010,000円 |
| 14級 | 560,000円 | 10,000円×56日分=560,000円 |
このように、後遺障害の等級が1つ変わるだけで、数十万円から100万円以上も受給できる金額が変わることがわかります。適正な後遺障害の等級認定を受けなければ、労災保険から支給される金額が少なくなり、大きな損をしてしまうリスクがあるのです。
また、会社に対して損害賠償請求をする場合も、後遺障害の等級に応じて逸失利益や慰謝料の金額が変わります。逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。
そのため、後遺障害の等級によって、労災保険から支給される補償の金額や会社に対して請求できる損害賠償の金額が大きく変わりますので、適切な後遺障害の等級認定を受けることがとても重要になるのです。
第3章 後遺障害等級認定の手続きの流れ
労災の後遺障害等級認定を受けるための手続きについて、具体的な流れを見ていきましょう。
まず、症状固定の診断を受けた後、主治医に労災保険の後遺障害診断書を作成してもらいます。
次に、この診断書と併せて、労働基準監督署に対して障害補償給付の申請書を提出します。
申請書類を提出した後、労働基準監督署において面談が実施されます。この面談では、提出された診断書やレントゲン写真などの資料だけではわからない症状について、被災者本人が直接説明することになります。
面談では、日常生活でどのような不自由を感じているか、痛みやしびれの程度はどの程度なのか、以前と比べてどのような作業が困難になったかなど、具体的に伝える必要があります。労働基準監督署の担当者は、これらの情報を総合的に判断して後遺障害の等級を決定するからです。
面談が終了すると、通常3か月程度で認定結果の通知書が届きます。無事に認定を受けることができれば、給付金が指定の口座へと振り込まれ、手続きは完了となります。
ただし、この一連の手続きにおいて最も重要になるのが、診断書の記載内容です。労働基準監督署は、主にこの診断書の内容に基づいて等級認定の判断を行うため、診断書に記載漏れや不正確な表現があると、あるべき後遺障害の認定が受けられない可能性があります。
また、面談においても、自身の症状を正確に伝えることができなければ、適切な評価を受けることが困難になってしまいます。初めての経験で緊張される方も多いですが、事前の準備が非常に重要になります。
第4章 適正な等級認定を受けるためのポイント
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを理解しておくことで、本来受けるべき等級認定を逃すリスクを大幅に減らすことができます。
まず、最も重要なのは診断書の記載内容です。労働基準監督署は、主に医師が作成した診断書に基づいて等級認定の判断を行います。しかし、医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではありません。
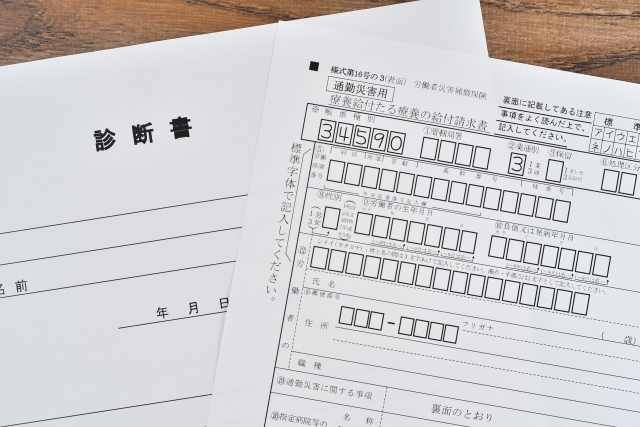
そのため、診断書に書いてもらう傷病名、症状である痛みやしびれの程度、必要な検査結果、関節の可動域について、被災者側から医師にしっかりと伝えなければ、記載漏れが生じて適正な後遺障害等級の認定が受けられないことがあります。
特に見落とされやすいのが、関節の可動域制限です。例えば、肩・肘・手首のいずれかの関節の可動域が健康な関節の可動域と比較して4分の3以下に制限されていれば12級の後遺障害に該当し、2分の1以下に制限されていれば10級の後遺障害に該当します。主治医が可動域制限を見過ごしてしまった場合、適切な後遺障害等級認定を受けられないリスクがあります。
次に、労働基準監督署での面談においても注意すべきポイントがあります。被災者は、自身の症状である痛みやしびれ、日常生活で不自由をしていること、労働能力が低下したことなどを労働基準監督署に対して正確に伝える必要があります。
しかし、初めての面談で緊張してしまい、本来伝えるべき症状を十分に説明できない方も少なくありません。事前に症状や日常生活での困りごとをメモにまとめておくなど、しっかりとした準備が必要です。
これらのポイントを一般の方がすべて把握し、適切に対応するのは決して簡単なことではありません。後遺障害等級認定に精通した専門家のサポートを受けることで、適正な認定を受けられる可能性が高まるのです。
まとめ

労災で後遺障害が残ると言われた方にとって、後遺障害等級認定は今後の人生を大きく左右する重要な手続きです。
まず理解していただきたいのは、後遺障害とは症状固定の時点で残っている症状のことであり、痛みやしびれ、関節の制限といった症状も含まれるということです。そして、後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級が1つ違うだけで受け取れる補償金が100万円以上も変わってしまうことは珍しくありません。
適正な等級認定を受けるためには、医師への適切な情報提供、可動域制限などの見落とされやすい症状への注意、労基署面談での症状の正確な説明など、専門的な知識と準備が必要です。
当事務所では、労災被害に遭われた方の後遺障害等級認定のサポートに力を入れており、適正な認定を受けるためのサポートを提供しております。
労災の後遺障害でお悩みの方、主治医から後遺障害が残るかもしれないと言われた方は、一人で悩まずに、まずは労災問題に詳しい弁護士にご相談ください。専門的な知識と経験を持つ弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、適正な補償を受けるためのサポートをいたします。











