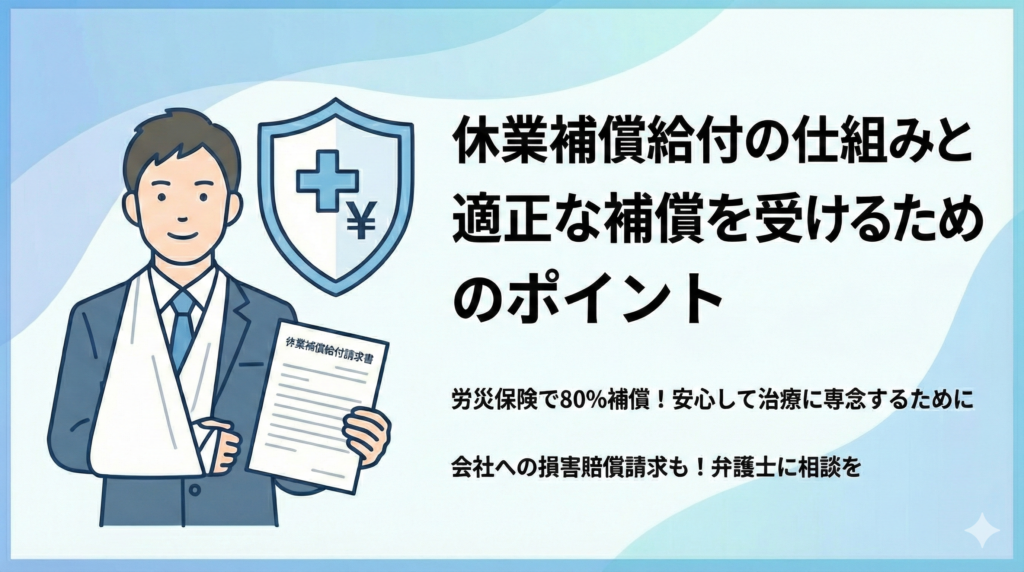
休業補償給付の仕組みと適正な補償を受けるためのポイント
労働災害に遭い、仕事を休まなければならなくなったとき、多くの方が「治療費はどうしよう」「生活費は大丈夫だろうか」と不安を抱えられるのではないでしょうか。
労災保険には、休業中の収入を補償してくれる「休業補償給付」という制度があり、この制度を利用することで、休業中も一定の収入を確保し、安心して治療に専念することができますが、実際にはこの制度だけでは補償が不十分な場合もあり、追加の対応が必要となることもあります。
私が労働災害を扱う弁護士として、ご相談をお受けしてきた中で、実際、労災で休業を余儀なくされた方の中には、十分な補償を受けられていないケースが少なくありませんでした。
本記事では、休業補償給付の基本的な仕組みから申請方法、さらには十分な補償を受けるためのポイントまで、詳しく解説していきます。
第1章 休業補償給付とは
休業補償給付は、労働災害により怪我や病気で働けなくなった労働者を支援するための制度で、労災保険から支給される給付金です。
例えば、工場での作業中の事故で怪我をしたり、長時間労働が原因で体調を崩したりして働けなくなった場合に、この制度を利用することができます。休業中の賃金補償として、給与の一定割合が支給されるため、治療に専念しながら生活を維持することができます。
第2章 休業補償給付を受けるための3つの要件
休業補償給付を受けるためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1. 労災の認定基準を満たすこと
まず第一の要件は、労災の認定基準を満たす必要があります。
業務災害の場合、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要素が必要です。例えば、工場での作業中の事故や、営業先での転倒事故などは、通常この要件を満たします。一方で、業務とは関係のない私的な活動中の事故は対象外となります。
通勤災害の場合は、通常の経路で通勤中に起きた事故であることが必要です。ただし、合理的な範囲内での経路の逸脱(例:日用品の購入のための立ち寄り)については認められる場合があります。
2. 労働することができないこと
第二の要件は、労働をすることができないことです。
この要件は、単に「体調が悪い」という自己判断だけでは不十分でで、医師による判断が必要となります。
労災保険の請求書には「診療担当者の証明」欄がありますので、ここに医師に記載をしてもらい、「労働することができないこと」を証明してもらうことが必要です。
3. 賃金を受けていないこと
第三の要件は、休業期間中に会社から賃金を受けていないことです。
例えば、会社の規定により休業中も給与が全額支払われる場合や、有給休暇を取得して給与が支給される場合は、休業補償給付を受けることはできません。
第3章 実際の補償内容と計算方法
休業補償給付では、休業1日につきどれくらいの補償が受けられるのでしょうか。具体的な金額の計算方法について、実例を交えながら説明していきます。
補償の基本的な仕組み
休業補償給付では、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。これは以下の2つから構成されています。
・休業補償給付:給付基礎日額の60%
・休業特別支給金:給付基礎日額の20%
給付基礎日額の計算方法
給付基礎日額は、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算出します。
具体的な計算例を見てみましょう。
<例>直近3ヶ月の給与が毎月20万円で、労災事故が7月に発生した場合
4月分:200,000円
5月分:200,000円
6月分:200,000円
合計:600,000円
給付基礎日額 = 600,000円 ÷ 91日(4~6月の暦日数)= 6,594円(1円未満は切り上げ)
この場合の1日当たりの休業補償給付(特別支給金含む)は、
6,594円 × 80% = 5,275円となります。
補償の対象となる期間
休業補償給付の対象となるのは、休業4日目以降です。最初の3日間は「待機期間」と呼ばれ、土日祝日など会社が休みの日でも1日と計算します。
原則として、労働者が職場復帰できる状態になるまで継続して受け取ることができます。
ただし、治療を続けても症状が改善せず「症状固定」したと医師が判断した時点で、完治していなくても、休業補償給付は終了となります。
なお、症状固定時に後遺障害が残った場合は、労働基準監督署へ申請し、後遺障害の等級認定を受けて、障害補償給付を新たに受給できる可能性があります。
年次有給休暇との関係
休業補償給付を受けられる場合でも、年次有給休暇を使うことはできます。
年次有給休暇を使用すれば賃金は100%支給されますが、将来使える有給休暇が減ってしまいます。一方、休業補償給付は賃金の80%の補償となりますが、有給休暇を温存できるメリットがあります。
第4章 申請手続きと注意点
申請の基本的な流れ
申請は労働基準監督署に対して行います。
【所定の請求書に必要事項を記入】
・業務災害の場合は「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)
・通勤災害の場合は「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)
【ポイント】
・請求書には医師と事業主の記載が必要です。医師の記載は、休業を要する状態であることの医学的な裏付けとなります。
・事業主の記載では、労働関係や賃金に関する情報を確認します。
・申請については、会社が請求を代行することも可能で、現実にはほとんどのケースで会社が申請を行っています。
必要書類の準備
請求には以下のような書類が必要となります。
・請求書(上記の様式)
・賃金台帳(写し)
・出勤簿(写し)
・その他労働基準監督署から求められた書類
時効に関する注意点
休業補償給付には2年の時効があります。これは実際に休業した日ごとに計算され、その翌日から起算します。
請求が遅れると受給できなくなる可能性があるため、早めの申請をお勧めします。
第5章 休業補償給付で十分でない場合の対応
休業補償給付は、労災による休業中の収入を一定程度保障する制度として重要な役割を果たしていますが、これだけでは十分な補償とはいえない場合があります。
このような場合、会社に対する損害賠償請求という方法を検討する必要があります。
会社への損害賠償請求
会社は労働者に対して、安全に働ける環境を整備する義務(安全配慮義務)を負っています。この義務が守られていなかったために労災が発生した場合、会社に対して損害賠償を請求することができます。
<請求できる損害の具体例>
・休業損害の40%部分(労災保険で補償されない部分・特別支給金は損益相殺の対象とならない)
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・通院交通費等
特に重要なのは、労災保険からは支給されない慰謝料の部分です。事故や後遺障害による精神的苦痛や、生活上の不便さに対する補償を受けることができます。
損害賠償請求の進め方
会社への損害賠償請求は、主に以下の手順で進めていきます。
1. 会社との示談交渉
会社との話し合いを試みます。話し合いが進展し、会社が責任を認め、具体的な賠償額が決まれば、解決ができます。
2. 訴訟
話し合いでの解決が難しい場合は、訴訟等の法的手続きを検討します。
弁護士に相談するメリット
このような損害賠償請求を進める際は、弁護士に相談することをお勧めします。
<弁護士に相談するメリット>
・損害額の適正な算定が可能
・交渉を専門家に任せられる
・法的な対応が必要な場合にもスムーズに移行できる
相談に来ていただいた際に、ご自身では気づかなかった損害項目が見つかることも少なくありません。
まとめ
本記事では、休業補償給付の仕組みと適正な補償を受けるためのポイントについて解説してきました。
休業補償給付は、労災により働けなくなった方の生活を支える重要な制度です。給付基礎日額の80%が補償され、治療に専念できる環境を整えることができます。
また、休業補償給付だけでは十分な補償が得られない場合、会社への損害賠償請求という選択肢もあります。 労災に遭われた方にとって、一番大切なのは安心して治療に専念できる環境です。補償の問題で悩まれている方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください










