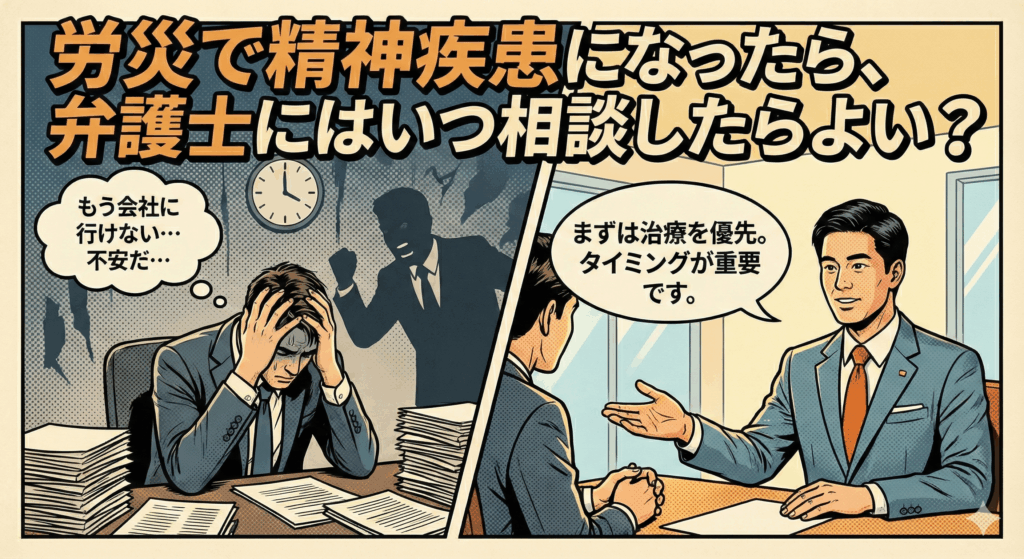
労災で精神疾患になったら、弁護士にはいつ相談したらよい?
上司からのパワハラで精神疾患を発症し、もう会社に行けない。長時間労働が続いて、うつ病になってしまった。そのような状況では、これからの治療や収入のことを考えると不安でいっぱいになってしまうのではないでしょうか。
「労災申請をした方がいいのだろうか」
「弁護士に相談した方がいいのだろうか」
「でも、今は心身ともに疲れ果てていて、何から始めていいのか分からない」
精神疾患の労災事案においては、私も、このような不安を抱える方々のご相談をうけることがあります。実は、精神疾患の労災の場合、「いつ、どのタイミングで弁護士に相談するのが最適か」という点が非常に重要になってきます。
なぜなら、精神疾患の治療には一定の時間がかかり、その経過によって受けられる補償の内容や、会社に請求できる損害賠償の範囲も変わってくるからです。
今回は、精神疾患の労災における弁護士相談のタイミングについて、お伝えしていきます。
第1章 増加する精神疾患の労災申請
精神疾患の労災申請は、近年急速に増加しています。厚生労働省の統計によれば、令和元年度に2,060件だった申請件数は、令和5年度には3,575件にまで増加しました。わずか5年間で申請件数が1.7倍以上に増えているのです。
しかし、申請すれば必ず労災として認定されるわけではありません。実際の認定率は31%~35%程度にとどまっています。つまり、申請者の3人に2人は労災として認定されていないことになります。
たとえ、会社や上司の対応に問題があったと感じていても、それだけでは労災として認定されません。労災として認定されるためには、法律で定められた要件を満たす必要があるため、精神疾患の労災認定には慎重な判断が必要となります。
特に精神疾患の場合、その症状や原因が目に見えにくく、証明が難しいという特徴があり、労災申請を考える前に、まずは適切な治療を受けることが何より重要になってきます。
第2章 なぜ治療を優先すべきか
精神疾患の労災では、まず治療に専念していただくことをお勧めしています。その理由は、精神疾患の治療には以下のような特徴があるからです。
治療には一定の時間が必要
例えば、うつ病の場合、一般的に回復までに半年から1年程度の期間が必要とされています。治療は「急性期」「回復期」「再発予防期」という段階を経て進んでいきます。また、様々な要因によって治療期間が長期化することもあり、再発の可能性も考慮する必要があります。
このように時間がかかる理由は、精神疾患からの回復には、心身の十分な休養と、じっくりとした治療が欠かせません。焦って早期の職場復帰を目指すことは、かえって症状を悪化させる可能性があります。
治療中の経済的支援
「治療に専念したいけれど、その間の収入はどうなるの?」
これは多くの方が不安に感じる点です。しかし、以下のような経済的支援の制度が用意されています。
まず、労災認定された場合、精神疾患の治療費は労災保険から全額支給されます。また、休業中は給料の約80%が休業補償給付として支給されます。
ただし、労災認定には一定の時間がかかるため、認定までの期間は傷病手当金の受給をお勧めしています。傷病手当金であれば、給料の約3分の2が補償されます。その後、労災認定された場合は、傷病手当金を返金し、より給付額の多い労災保険からの補償に切り替えることができます。
症状固定と後遺障害
労災保険による治療は「症状固定」と判断されるまで継続することができます。
(症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の症状の改善が見込めないと判断される状態を指します。)
重要なのは、症状固定時に後遺障害が残った場合、その等級に応じて労災保険から補償を受けることができるという点です。うつ病などの非器質性精神障害の場合、第9級、第12級、第14級のいずれかに認定される可能性があります。
例えば第9級に認定された場合、就労可能な職種が相当な程度に制限される状態として、障害補償一時金などが支給されます。このような補償を適切に受けるためにも、主治医としっかりと相談しながら、必要な期間の治療を受けることが大切です。
第3章 労災申請の3つの要件
精神疾患の労災申請では、以下の3つの要件を満たす必要があります。特に重要なのは、業務による強い心理的負荷の存在を客観的に証明することです。
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②精神障害を発症する前のおおむね6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷があったこと
③業務以外の要因による発病ではないこと
精神疾患の労災申請は、詳しくは下記の記事を参考にしてください。
第4章 会社への損害賠償請求の可能性
労災認定を受けた場合でも、労災保険からの補償だけでは十分でないケースがあります。そのような場合、会社に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
労災保険と損害賠償の関係
労災保険からは、治療費や休業補償、後遺障害に対する補償が支給されます。しかし、精神的苦痛に対する慰謝料は支給されません。また、後遺障害による将来の収入減少についても、労災保険の補償だけでは十分にカバーできない場合があります。
このような労災保険では補填されない損害について、会社の安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求を行うことができます。
<安全配慮義務違反の考え方>
安全配慮義務とは、従業員の心身の健康を守るために会社が負う法的義務です。具体的には、以下のような場合に安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
【長時間労働の場合】
・労働時間の適切な把握を怠っていた
・過重労働の実態を知りながら、負担軽減措置を取らなかった
・健康を悪化させていることを知りながら、過重な業務を継続させた
【パワハラの場合】
・相談窓口が設置されていなかった
・パワハラの相談があったにもかかわらず、適切な調査を行わなかった
・パワハラの事実を認識しながら、加害者への処分や被害者の保護等の対策を怠った
会社のこれらの義務違反と、精神疾患の発症との間に因果関係が認められれば、損害賠償請求が可能となります。
第5章 弁護士への相談タイミングについて
精神疾患の労災では、まず十分な治療を受けることが重要です。
症状が安定してきた段階で弁護士に相談することで、より適切な補償を受けられる可能性が高まりますので、早急な法的対応を急ぐよりも、自身の回復に重点を置くことが、結果として最善の解決につながります。
そのため、以下のような状況になった際に、弁護士への相談をおすすめします。
・症状が安定してきた
・主治医から症状固定の見通しが示された
・復職や退職を検討する段階になった
・会社との交渉が必要になった
まとめ:労災で精神疾患となった場合の対応について
最後に、状況に応じた対応の方針についてまとめておきます。
精神疾患の労災においては、以下の順序で対応することをお勧めします。
まずは治療に専念
・主治医としっかり相談し、必要な治療を受ける
・傷病手当金を活用して、当面の生活費を確保する
・症状や通院の記録、職場でのストレス要因を記録として残しておく
症状が安定してきたら
・労災申請に必要な証拠を整理する
・長時間労働やパワハラ等の証拠を集める
・この段階で弁護士に相談し、労災申請の準備を始める
症状固定後
・後遺障害の等級認定の準備
・会社への損害賠償請求の検討
・将来の働き方について検討
私たちは、労災の被害に遭われた方が、一日も早く心身の健康を取り戻し、前を向いて歩み出せるよう、専門的な知識と経験を活かしてサポートいたします。 現在の症状や状況に不安を感じていらっしゃる方は、まずは無料相談をご利用ください。










